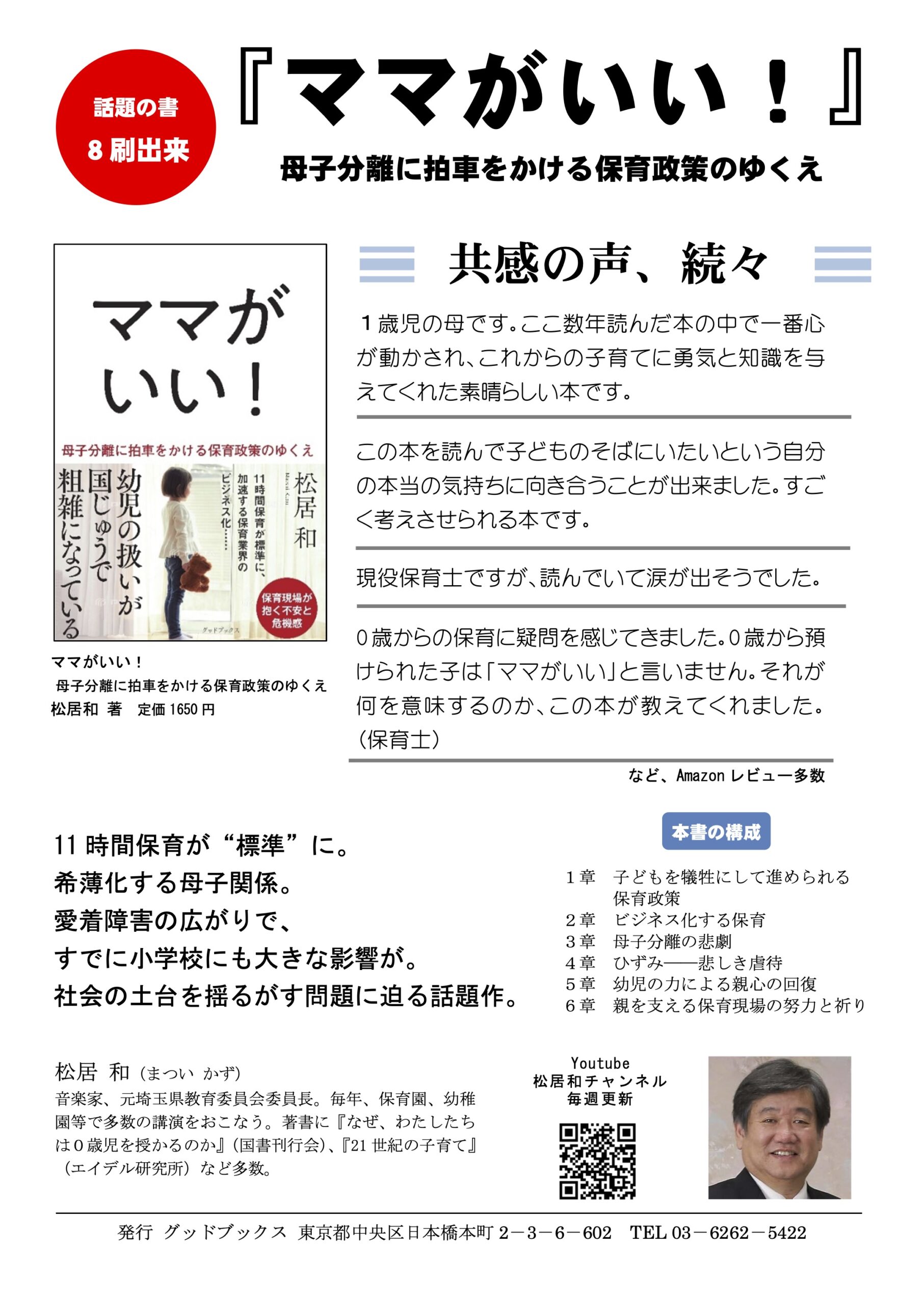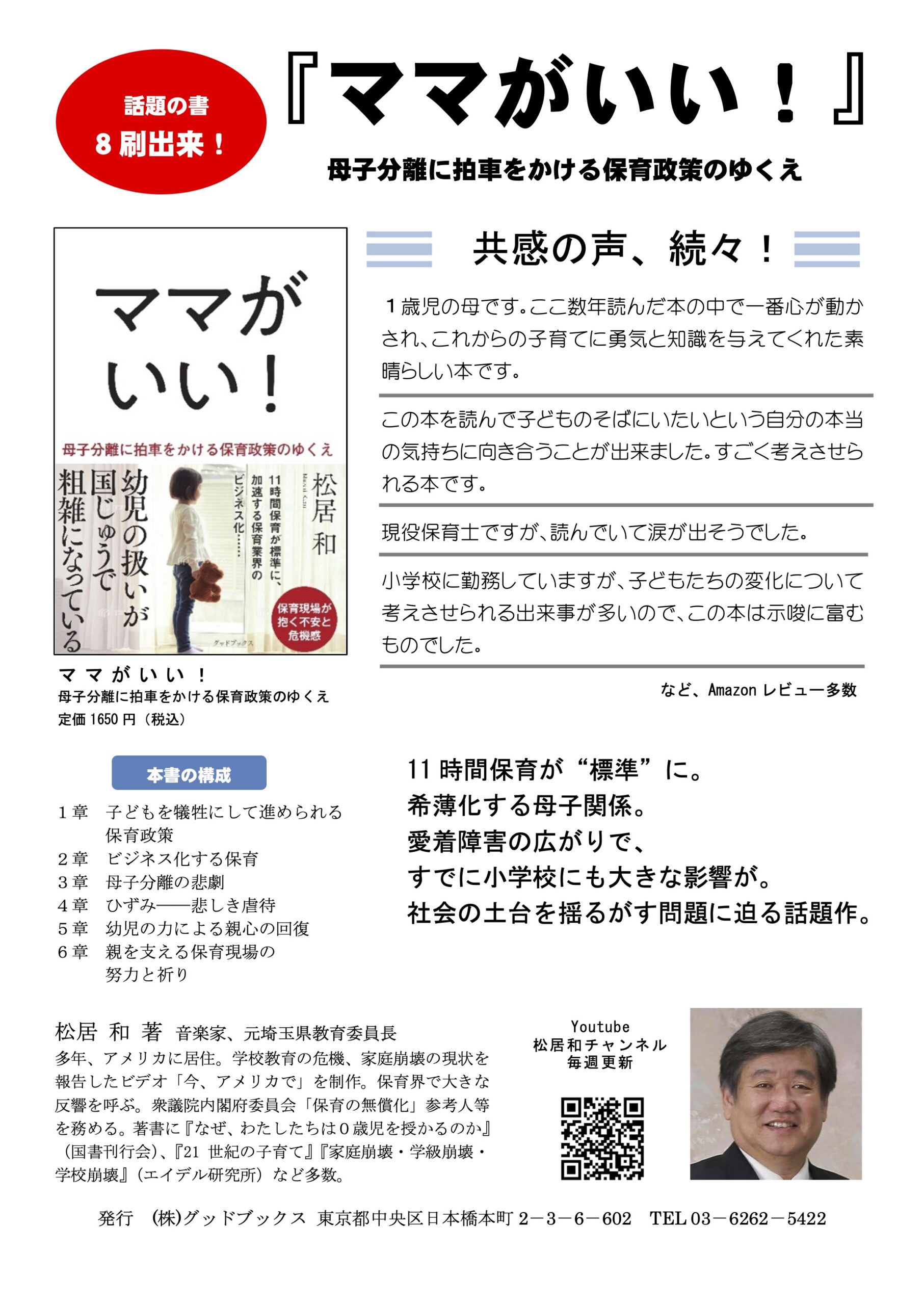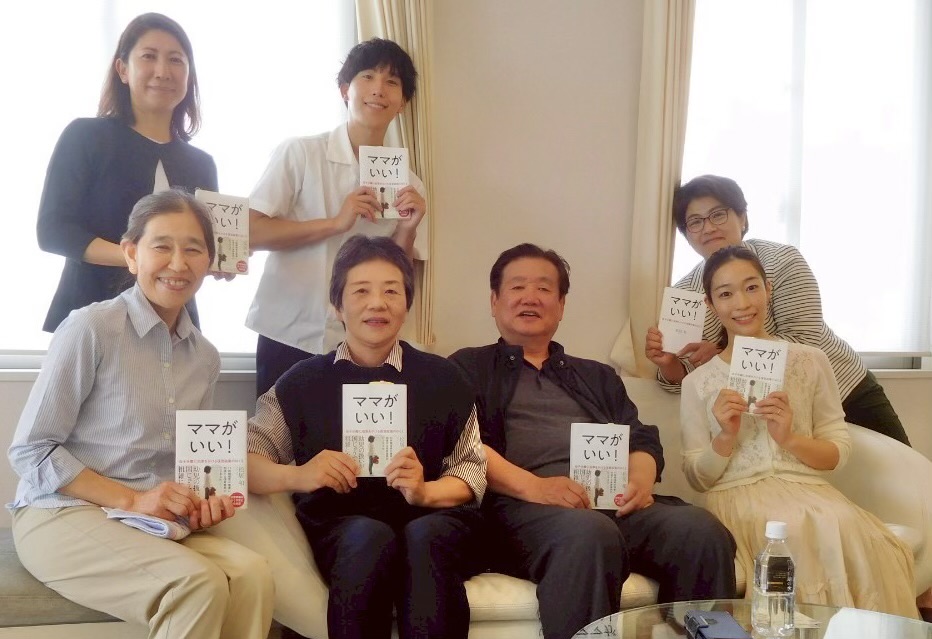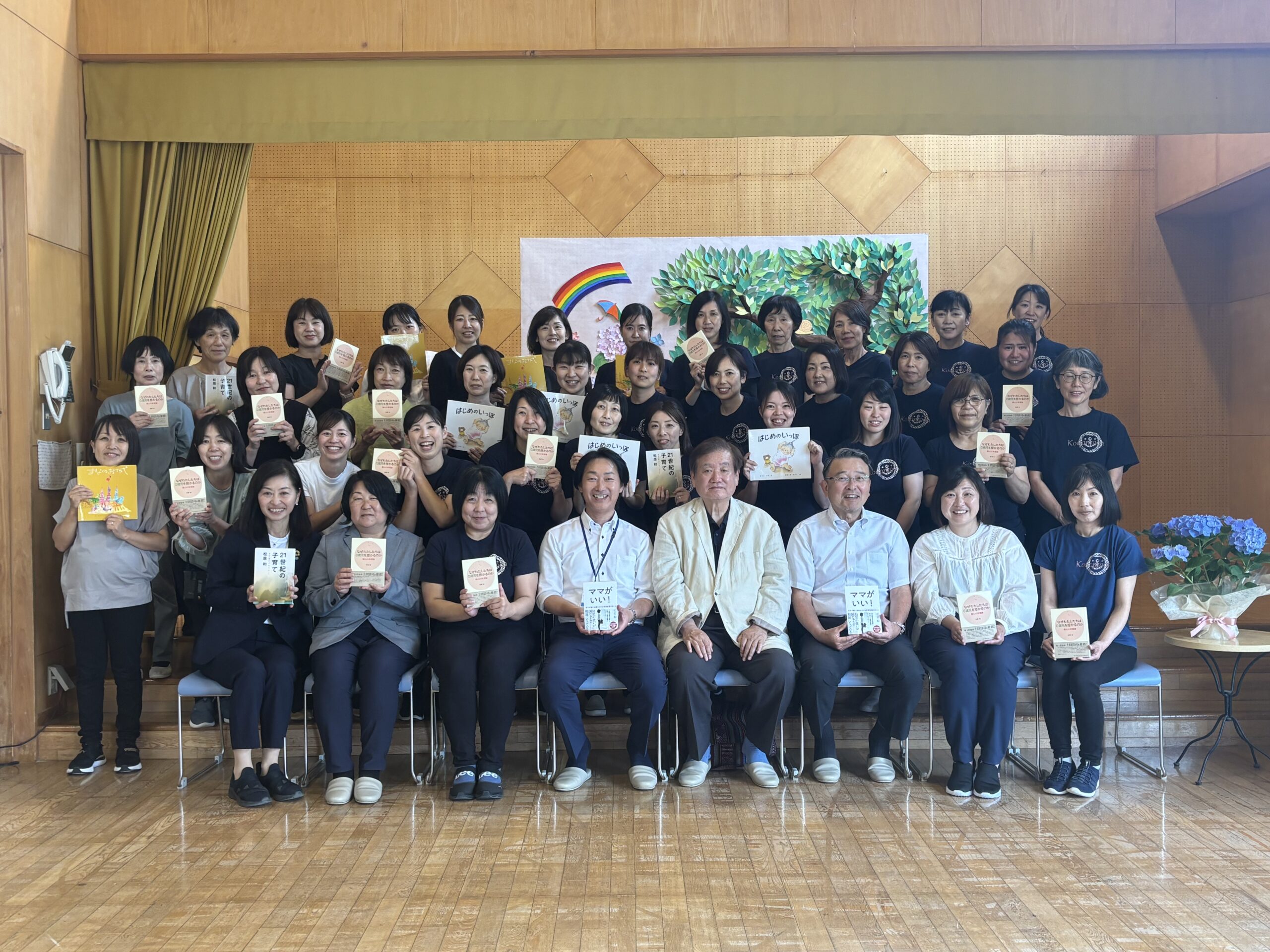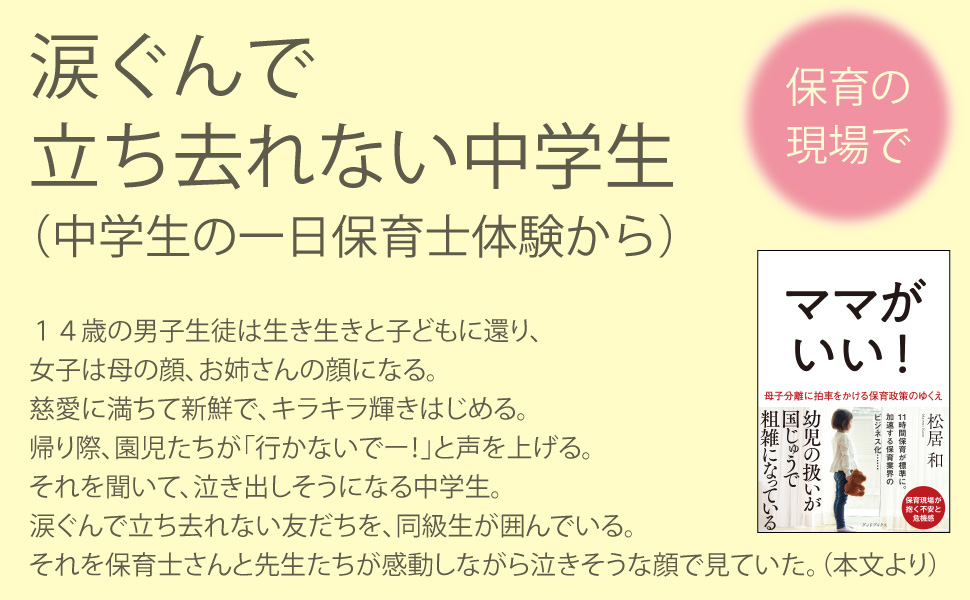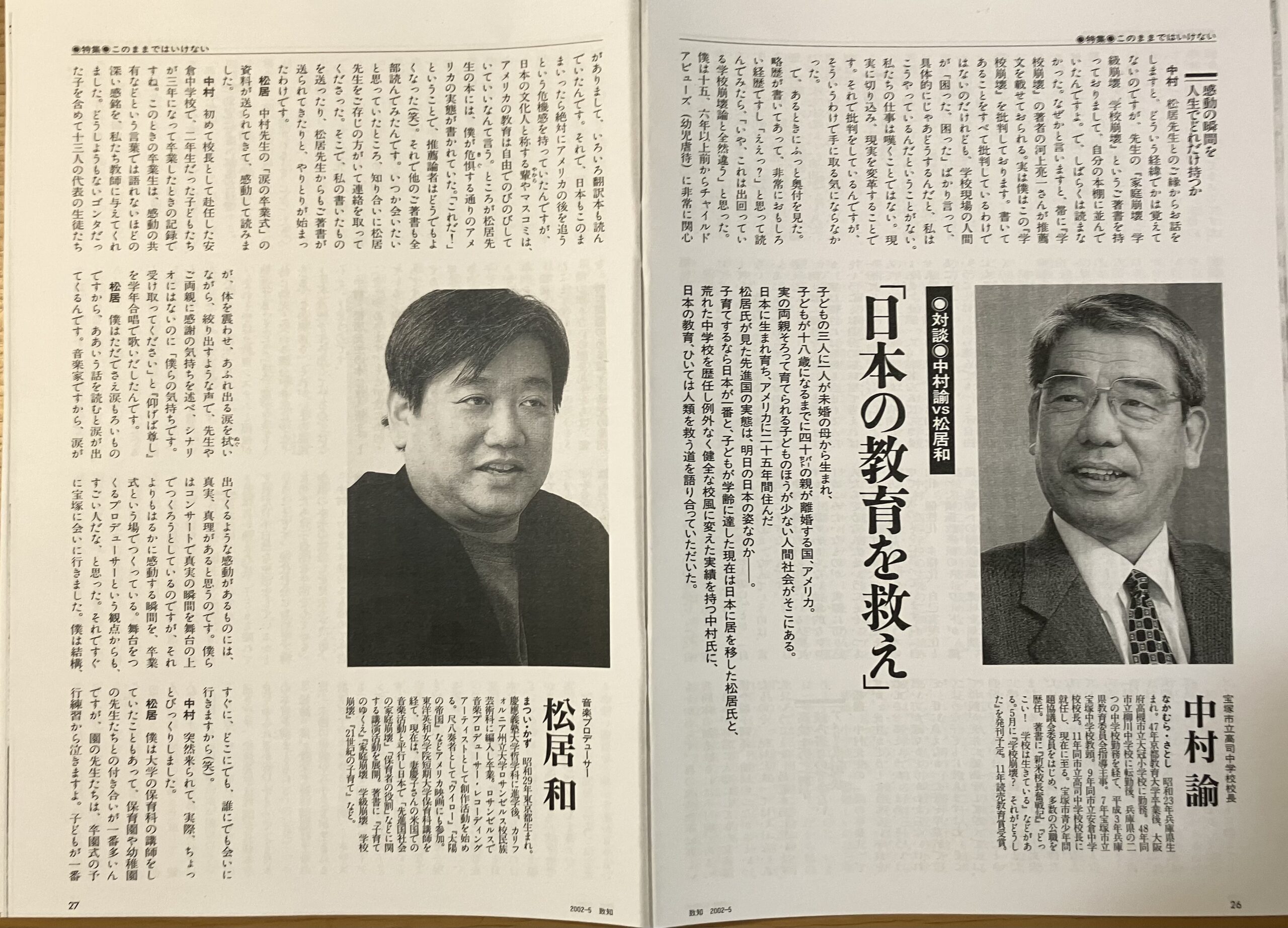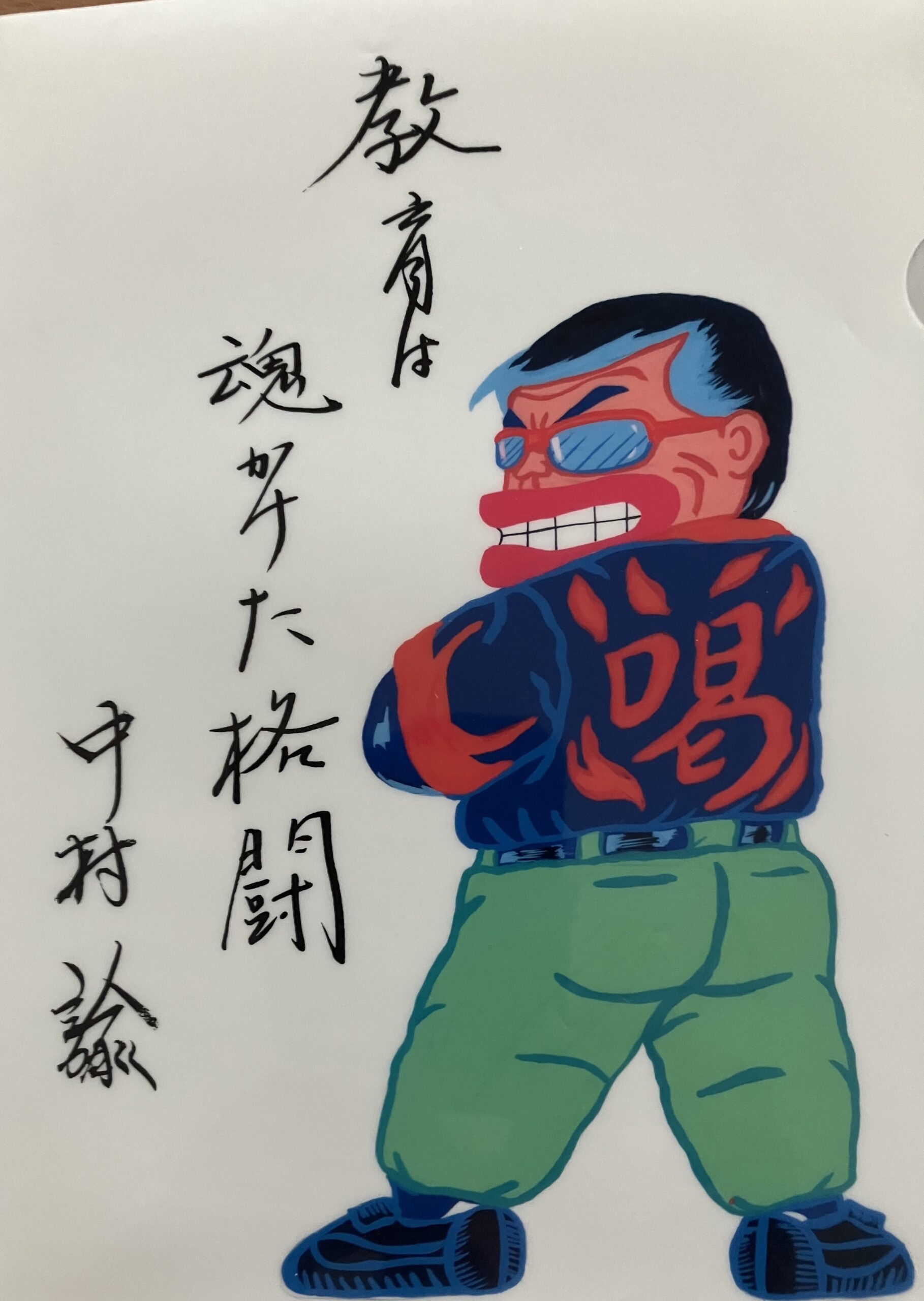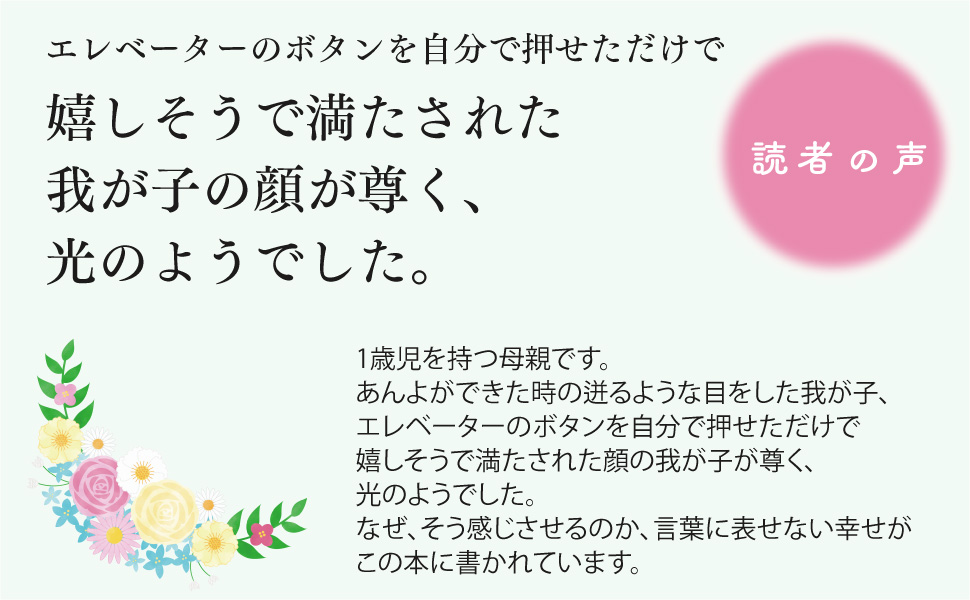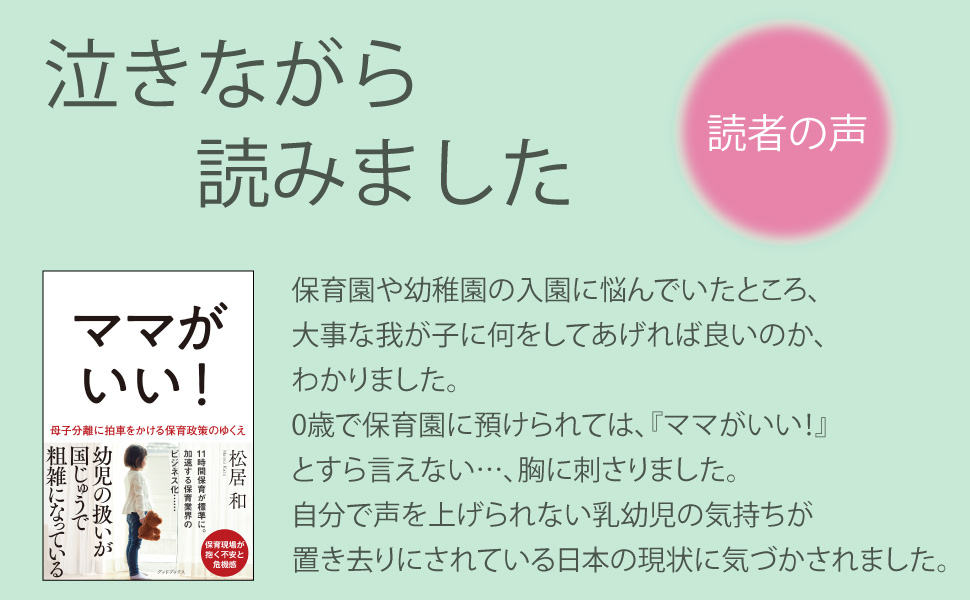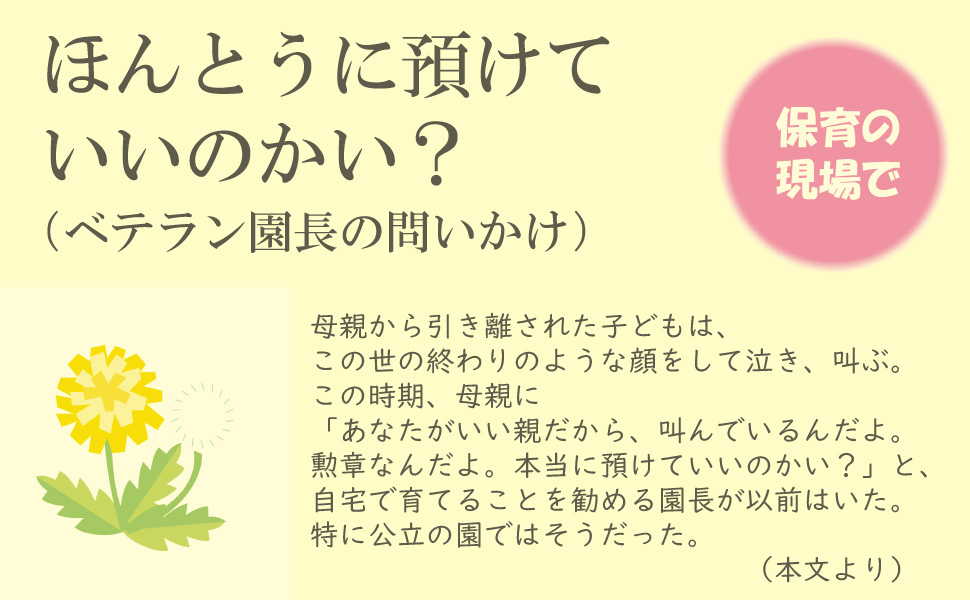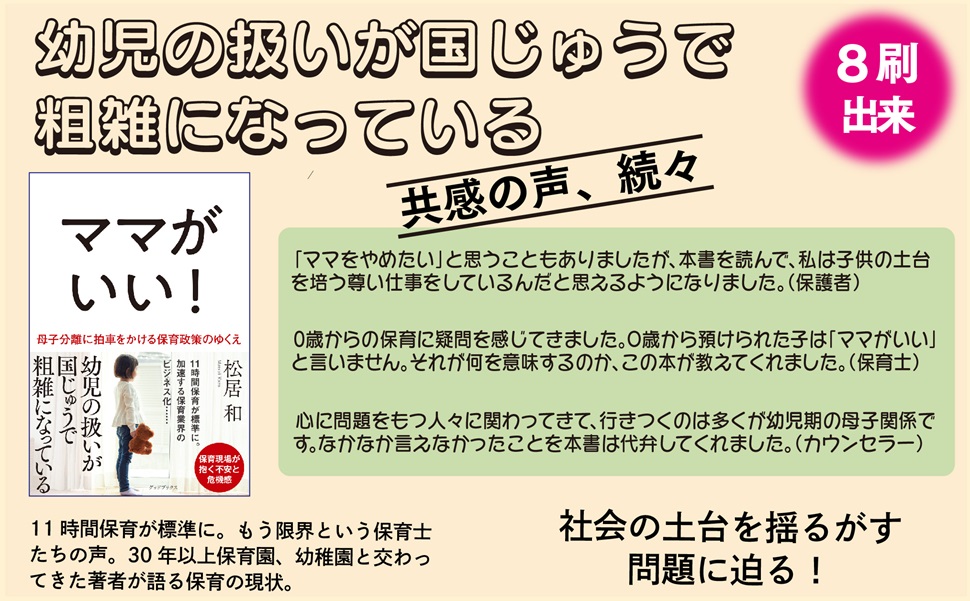松居和チャンネル 第77回、
(テーマは)「ワーキングマザー」の短歌集、です。
副題は、「自分のためだけに、存在してほしいと、子どもは望む」としました。
(「ママがいい!」のAmazonのレビューです。
1歳児を持つ母親です。
育児の本質と、その育児がどう社会的に影響するのか、までが書かれています。
ちょうど子供がお腹の風邪で体調が悪く心配で、夜中も起きて子供を見ておこうと眠気覚ましに購入しました。
筆者の口調は強いですが、情熱的で、詩的で、美しいです。
(ここから私)
このレビューは嬉しい。
そして、講演に来てくださった浅羽佐和子さんからいただいた、「いつも空をみて」という短歌集を、今回は紹介しました。
そこには、身が引き締まるような、母の「本音」が詠まれていた。
「句集」からにじみ出る母の苦しみや、悲しみは、いい母親であるほど増してゆく。
だからと言って、この葛藤を、不公平だと、見ないふりをしたり、意図的に減らしてゆくと、同じ量の悲しみを、知らないうちに幼児たちが、負っていく。
悲しみは連鎖し、やがて増幅してゆく。
いい親であるがゆえの、母親の、苦しみや悲しみは、そのまま負っていけば、やがて喜びや期待になって、別の道筋に、導かれてゆくのだと思う。
親は、子どもの寝顔に幸せを感じるといいます。
目の前で、安心し、眠っている姿に、自分の真の価値を知る。
ワーキングマザーは、結果を求める世界に生きています。
しかし、母親は、いい親でいたい、と思った瞬間、すでに「いい親」です。
結果ではなく、その親の心持ちに価値があるのです。