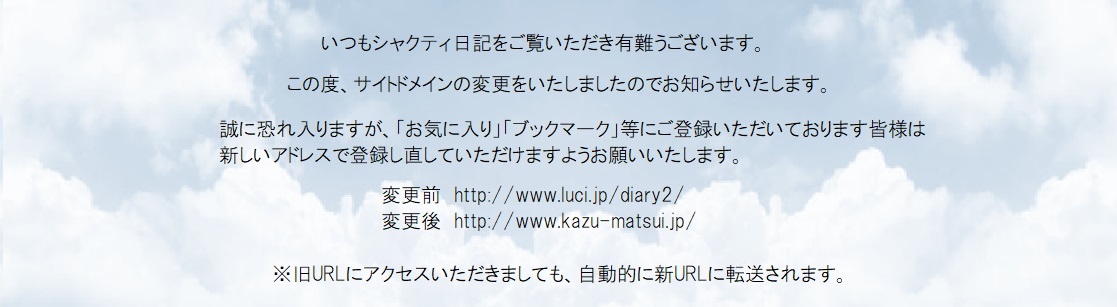インドから帰って、2日後に新潟国体の開会式で埼玉県選手団と一緒に行進し、ずっと昔中学校で習った「若い力」を合唱しました。こんなことでちょっと涙が出そうになります。スタジアム全体が歌うことで心を一つにする感じが、今の私にはいいのです。そのあとの会で、皇后様と少しだけお話することが出来ました。
月別: 9月 2009
待っている人たち
明日、シャクティから離れます。
今回、シャクティの娘たちは、暇があれば紙漉きをしていました。
私の友人がシャクティの作るバナナの紙がカリグラフィーにいいと言って注文したからです。紙が作られる行程を一日見ていると、ゆっくり流れる時間が立体的に見えてきます。太陽も手伝って、温もりが紙に沁みていくのが感じられます。焦りがないのです。
センターに居ると、シャクティの娘たちが、待っている人たちのような気がしてきます。何かが起こるのを待っている、待っていると起こる。そして、信頼があれば、それはきっと良いことで、絆があればいつか必ず安心につながる。だから待って、待ちながら、時々踊る。
すると、すべてが回り始める。大きく一体になって、輪になって踊りが始まる。
トールキンが「指輪物語」で表現したホビット族が尊重する社会の安心感かもしれません。力と欲の黒い影から世の中を守るのは、こうした人たちの日々の営みと楽しみだと言いたかったのだと思います。

セルバとモルゲスワリを訪問
ソウバさんの車が直って、セルバとモルゲスワリの家へ出かけました。田舎道を車で一時間、美しい田園風景の中に一軒家がありました。「あそこだ」とソウバさんが車を止めて指差しました。私は、あわててカメラをバッグから出しました。
三脚を持って、少し手間取っている間に、ソウバさんとシスターはあぜ道を先に歩いて行きます。その後ろ姿を撮っていると、ファインダーの中に小さくセルバが見えました。私は、思わず手を振りました。
セルバの息子は3才になっていました。ご主人はハンサムで誠実そうな人でした。ご主人の両親とご主人の弟夫婦とその一歳の息子と、セルバは屋上のある小さな石の家に暮らしていました。まわりには、ネギの畑とぶどう畑がありました。褐色の土と青い空、緑の林、そのコントラストの中にセルバは生きていました。彼女はやっぱり黒系の服を着ていました。そして、踊っていた時よりも少しだけ太って、普通の感じがしました。その温かさが3才の息子を包み込んでいました。記念写真を撮りました。(日本に帰ったら、この記事につけますね。)

そこから、30分ほどディンディガルの方向へ戻ったところにモルゲスワリの家がありました。道ばたの小さな村の大きな木の下に彼女は住んでいました。
セルバと違って、モルゲスワリは結婚しないで、もう少し長くシャクティに居たがっていたのを私は知っていました。ですから、少し心配していましたが、モルゲスワリは二人目の子をお腹に宿し、娘と二人で小さな家に住んでいました。ご主人は出稼ぎに出ることが多く、この日も居ませんでした。でも、モルゲスワリが退屈しないよう、衛星放送が見れるよう家にはフライパンのようなアンテナが屋根についていました。玄関外の雨にさらされた貧弱な釜戸と比べるとちょっとちぐはぐなアンテナが、一家の確かさを示して嬉しそうでした。
私は、ドキュメンタリーの中で、彼女の母親が、女の子にはテレビは見せません、と確信を持って語っていたのを思い出しました。
モルゲスワリの娘は、やんちゃで暴れん坊でした。はにかみ屋で物静かな母親は、それでもちゃんと目で、一つ所にじっとしていない娘を笑いながら追っています。
片足をひもで木に結わえられたアヒルに、娘がちょっと意地悪をしました。モルゲスワリが、すみません、というようにシスターを見ました。シスターが声を出して笑い、ソウバさんと私も娘を眺めながら楽しい時間を過ごしました。
(日本に帰ったら、このやんちゃ娘の写真をこの記事に載せます。)
言葉の通じない時間が、ゆっくりと過ぎてゆきます。言葉がわからないから、繊細になる感覚の中で、私は考えます。0才児や1才児との言葉のない会話の意味を。何かを知ることよりも、知ろうとすることが体験であることを。
シャクティ日本公演にあたって
シスター・チャンドラとシャクティの踊り手たちの存在についてお話しする時に、どうしも知っていただきたいのは、インドのカースト制と女性差別の問題です。カースト制と言っても「不可触民」と翻訳されているダリットは、カースト外、いわゆるアウトカースト、人にあらずと見なされて来た人たちです。インドの人口の20%と言われています。
去年もCNNのニュースで、ダリットの少女が、ダリットが通ってはいけない小道を歩いて、火に投げ込まれるという事件が報じられていました。いまだに、女の子が生まれると間引きされることがあります。シャクティが踊るダンス劇の中にもそのシーンが出てきます。太鼓を赤ん坊に見立て演じられるこの場面は、インド人ならすぐに理解する場面ですが、私は前回の公演でも、映画の中でもとりたててそれを説明することはしませんでした。言葉や説明がないから見えてくるものがあると思うからです。それについて、シスターとじっくり話したこともあります。
こうした様々な問題に、村の少女たちを集め、将来村の女性のリーダーとなってほしいと願い、地を這うような意識改革を目指してシスターが創ったのがシャクティセンターです。
シスターは少女たちに踊りを教えます。特に、タップーと呼ばれる太鼓を叩きながら踊るパラヤッタムは、本来代々その職を受け継いできたダリットの男性によって、上位カーストの人の葬式で踊られて来たものでした。その太鼓を女性が叩き、ステージで踊ることは、それだけでカーストの壁を二重三重に破ることになるのです。だからこそ、社会的反発もあり、見るものの魂を揺さぶるのかもしれません。ステージで見せる少女たちの不思議な力強さと輝きは、過去に虐げられ苦しんできた人たちの悲しみ、怒り、そして歓びさえも、伝えている気がします。
少女たちのシャクティセンターでの一日は、踊りの練習をのぞけば、どちらかと言えば淡々としていて平和です。
少女たちを私が一言で表現しようとすれが、たぶん、「育ちがいい」という言葉が一番似合うでしょうか。生き生きしていて、自制心があり、優しさがあって、はにかみがあって、目が会うと何かが燃え上がり人間同士の絆を感じる、「私はここにいるよ」と語りかけて来る。その子たちの幾人かは、親が原因で家庭に居られなくなった子です。村人が相談してシャクティに預けに来た子もいるのです。それなのに…。
シスターが言う、「集まること」そして「わかちあうこと」が、村単位だからでしょうか。
籠を編んだり、紙を漉いたり、集まって新聞を読みあって意見を交わしたり、その少女たちが時々見せる野生の表情。シスターがしっかり押さえていないと、火花が散りそうな瞬間、秘めている炎が垣間見える時があるのです。
「人間はなぜ踊るのか」
映画を作った時のあのテーマが私の中に蘇ってきます。
この子たちに救われた、と感じます。
シャクティの子たち
シスターのオフィスでソウバさんを待ちながら話をしていました。庭に夕暮れが迫り、マドライから仕事を済ませ正午には来るはずのソウバさんは、7時間遅れ。それが気にならない空気が、夕食の支度をする煙に混じって漂っています。21人の踊り手たちの話す声が聞こえます。ここへ来ると、私は言語から解放され、ちょっとした一人の間抜けになれるのです。タミル語はまったくわからないのですから。言葉のわかる話し相手はシスターと助手のシスター?フロリスだけです。
今日は、三人でセルバの家を訊ねるはずでした。ドキュメンタリー映画で婚約が決まったセルバにインタビューをしたのが5年前、今は子どもがいるセルバにもう一度会って、その顔を見たかったのです。彼女は私の一番好きなダンサーでした。生まれつきの自分の型を持っていて、ちょっと目には、マッチ棒が踊っている感じですが、その動きが誰にも真似出来ない、フレッド・アステア風のストリート感を持っているのです。観客を意識することがまったくない動きは、自然で、ふだんの立ち居振る舞いと少しも変わらない、生きていることが踊っていること、そんなセルバでした。
私は、セルバに会うためにその朝わざわざ髭を剃りました。女性に会うと言うよりも野生の女神に再会するような気持ちでした。
シスターが、「最近日本での講演ではどんなことを話している?」と訊きました。
私は、最近講演で話している4才児完成説、赤ん坊が意図せずまわりの人をいい人間にし、社会の心を一つにする話、園長が道祖神になってゆく話(興味のある方は、私のホームページの「原稿集」を読んでみて下さい)を、英語に少しずつ翻訳しながら話しました。
シスターは、祖父母心が人間社会においてどれだけ大切か、という話になった時に目を輝かせて「そうなの。おじいちゃんおばあちゃんは特別な人たちですね」と嬉しそうでした。0才から4才までと死ぬ直前に人間が強く「教えるモード」に入ること、真ん中に居る人たちは、この宇宙に近い両側が幸せそうにしていることで安心すること、だから幼児を神と見ればいいんだと思います、と話しました。カソリックの修道女に神や宇宙という言葉を使うにはちょっと勇気が要りますが、シスターには使えます。
青山学院の伊藤先生から、シスターがお祈りを捧げ、聖書を読み、踊り手たちが踊る礼拝の、シスターのメッセージのタイトルをメールで聴かれていました。
シスターは、「もちろん“Coming together”ですよ」と笑いました。
ドキュメンタリーの中で、幸せとはなんですか?という私の質問に答えてシスターが言った「集まること」。そして、人間の美しさは「わかちあうこと」という、この二つの柱は、考える時、私の中で生き続けています。聖書の朗読はPhilip:2:1-5になりました。
天井で蚊よけのファンがゆっくり回っているシスターの小さなオフィスにいると、頻繁に電話のベルが鳴ります。少女たちの実家からかかってくるのです。3ヶ月コースの子たちは、まだ家を離れて日が浅いので、たぶん親からかかってくるのです。
一人の女の子が、長電話で受話器の向こうにいる誰かに必死に話しています。
「母親に話しているのよ」とシスターが言います。「小さな妹をぶってはいけないって言ってるの。あなたが言う、子どもが大人を育てている見本よ」
電話が終わって、その子はちょっと泣き出しそうな顔でオフィスを出て行きました。外はもう真っ暗です。ソウバさんから車が故障した、という電話がかかってきました。
インドに打ち合わせに来ています
チェンナイの空港に、、親友のソウバさんが迎えに来てくれました。ソウバさんはシスターの一番の応援者で、こちらのJAYAテレビでドキュメンタリーを制作している人です。私がドキュメンタリー映画「シスター・チャンドラとシャクティの踊り手たち」を作った時にも、色々とアドバイスをしてくれた陰の助監督、映像の中にも登場します。ちょっと髪の薄くなった彼の笑顔が何よりの歓迎でした。
次の日、マドライ空港でシスターの出迎えを受けました。
新しく出来たハイウエイを飛ばしてシャクティセンターに向かう途中、ソウバさんの農園に寄りました。以前撮影の時にも使った藁葺き小屋の小さな別荘の他に、もう一軒エアコン付きの新しい家が建っていました。街の喧噪を素通りしてここへやって来ると、荒野の中に昔のインドを感じます。移動手段がいまほど発達していなかった頃のインドは、たぶんどこへ行ってもこんな感じだったのかもしれません。私は、実を言うとインドの都会が苦手です。
2時間かけて、門番と、シスターと一緒に迎えに来てくれていたエスターが料理をしてくれ、それを食べて少し話をし、昼寝をしました。大地の上で安らいだのかもしれません。目を覚ますともう辺りは夕暮れで、山の向こうで雷が光っています。
シャクティセンターに着いた頃にはすっかり暗くなっていました。警笛の音を聴きつけて、みんなが並んで出迎えてくれました。黒板に、Welcome Kazu san to Sakthiと書いてありました。黒板の上には、一昨年亡くなったシスター・アナンシアの写真がかかっていました。アナンシアが居て、三世代のシャクティファミリーだったなあ、と思います。
私が、アナンシアのチャテゥニーと呼んで大好物だったあの味のチャテゥニーをドセイにのせて食べました。懐かしい味でした。シンプルですが、いくつかの層になった微かな深みをはっきりと感じる、南インド特有の文化がありました。
シスターがカレイに「カズさんに、アナンシアのチャテゥニーをもう少し持ってきてあげて」と言いました。写真のアナンシアが笑っています。変わらない、いつもの風景がありました。新しく入ったメンバーたちが順番に挨拶に来ました。名前は覚えきれませんでした。
この子たちの笑顔はなんでこんなに生き生きしているのだろう。
日本から着いたばかりだと一層はっきり感じられるのです。大地の子、そんな言葉がぴったりの、少し野生の子たちです。
きっと、いまごろこの子たちの実家では、小さなランプの火をつけて、両親が妹たちと黙ってご飯を食べているのでしょうか。