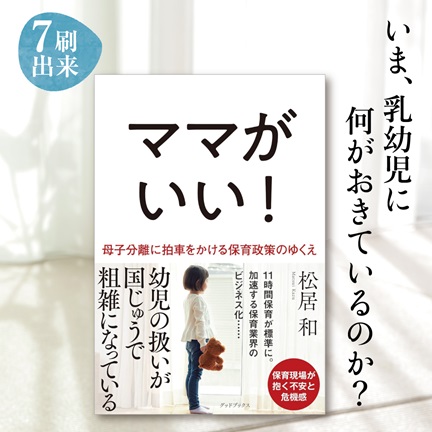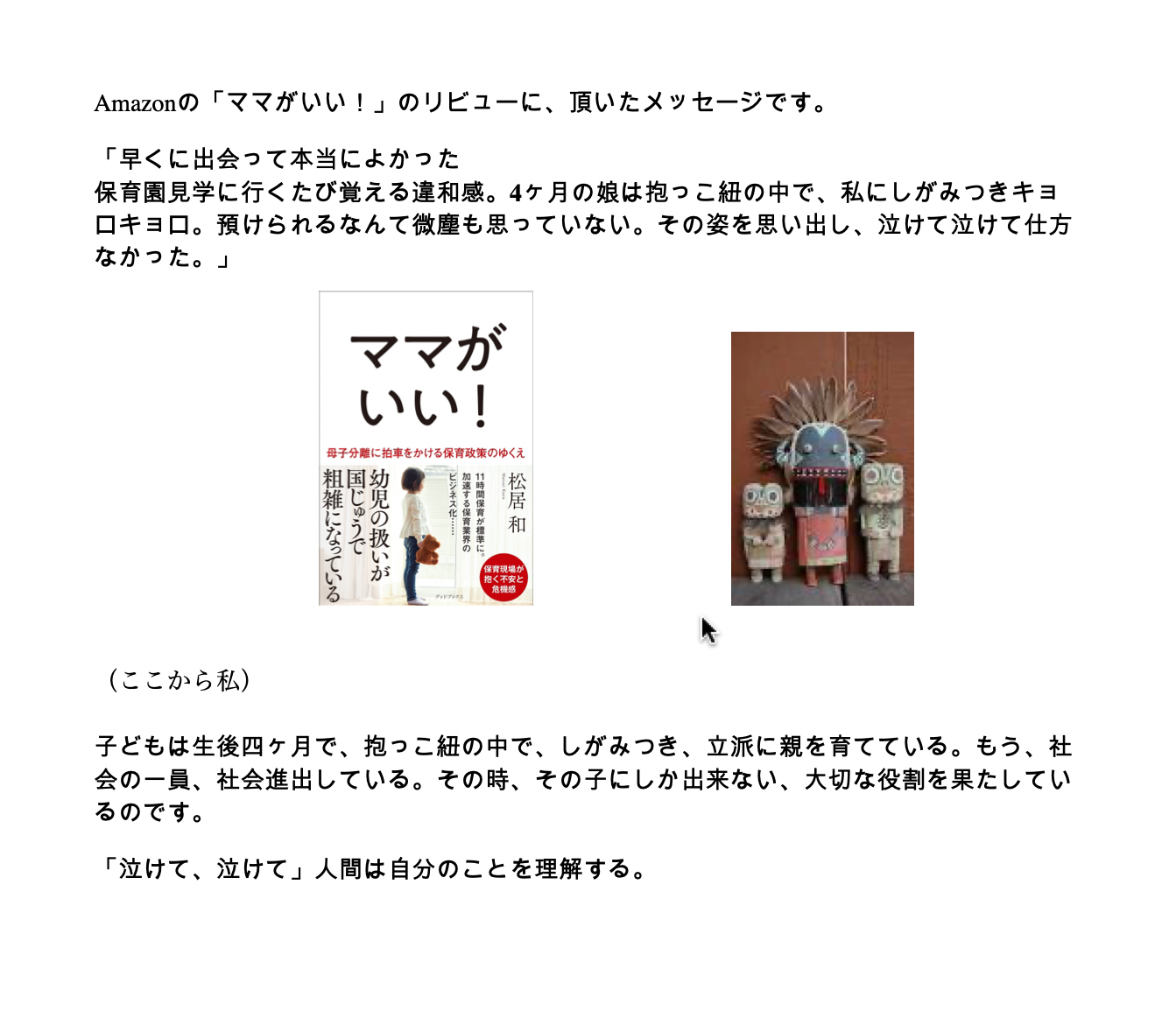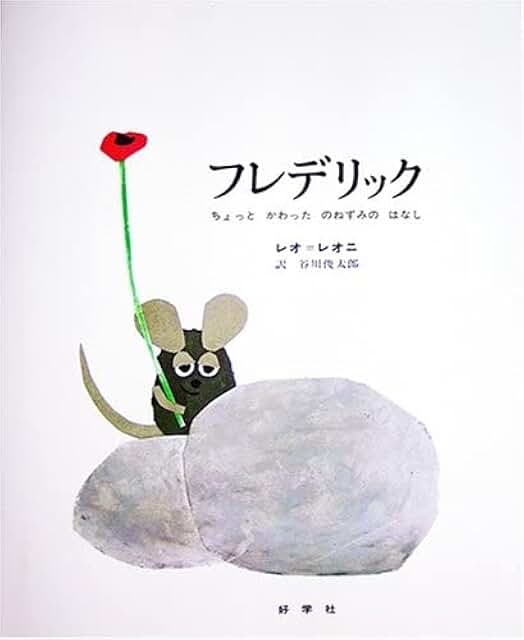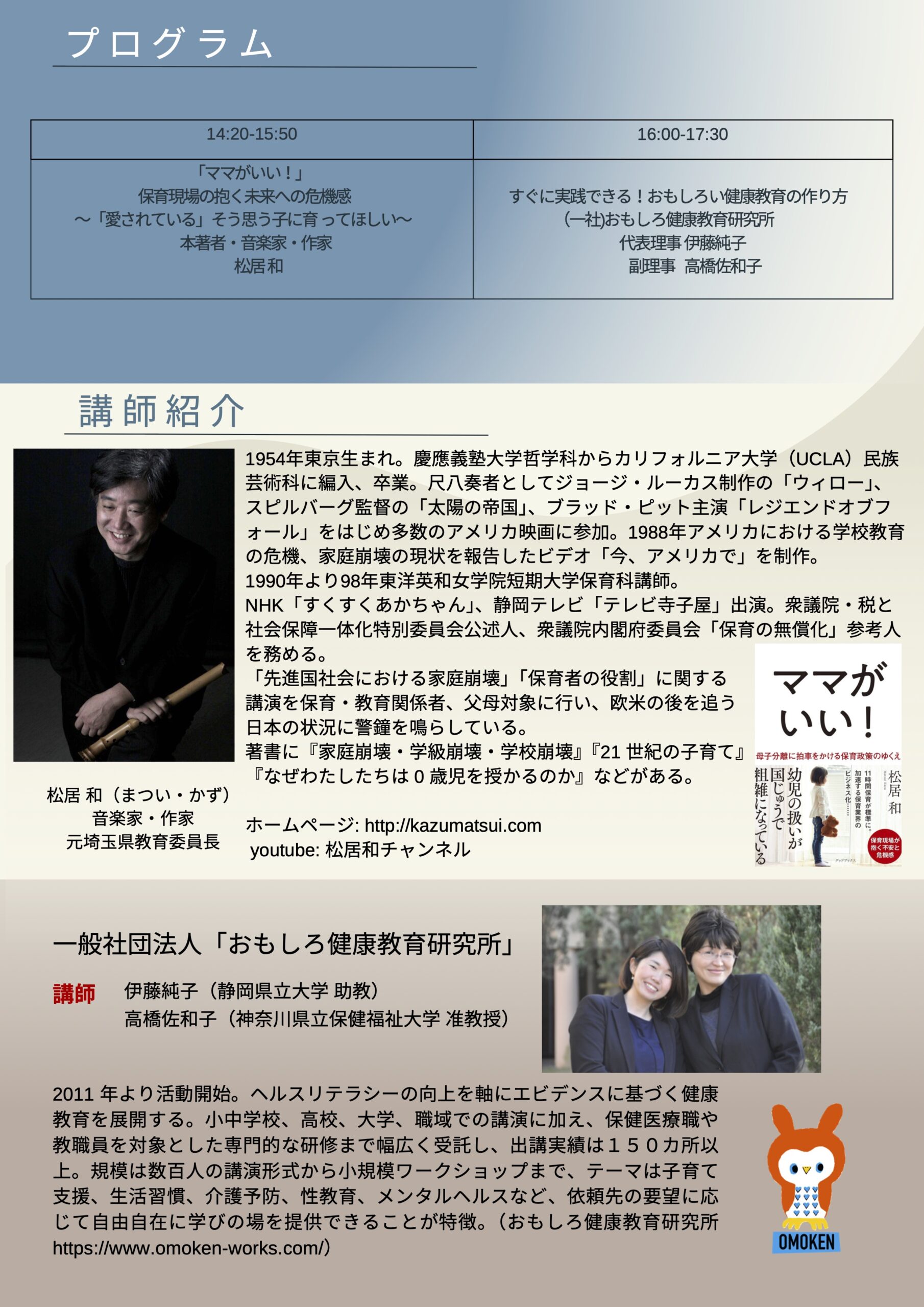さすが、日本!
チャンネルの第55回では、こんな記事を取り上げました。
(AERA 2024年11月25日号より)
「仕事一筋、“昭和の男”が「孫休暇」取得なぜ? 子どもの世話、妻に任せきりだった後悔」
~企業や自治体で仕事と家庭の両立支援が進むなか、孫のために休暇を取れる制度が広がっている。具体的にどのようなものなのか。「孫休暇」を設ける九州電力を取材した。~
(ここから私)
子どもの人生に、まだ、祖父母が存在している国なのです。
こういう努力が広がる気配が、いま、ある。
日本の底力です。
経済競争に気を取られ、「情報」で考え、自分のいい人間性に気付かず過ごしてきた男たちの、後悔と反省は、孫たちによって、突然、花開き、輝く。
「子どもを可愛がることに、幸せを感じる」遺伝子が、慌てて、オンになる。
頼り切り、信じ切り、幸せそう。
その境地が、孫と、ピッタリ重なっていく。
この人たちが、弱者に寄り添い、調和のシンボルになり、小波のように、社会に「鎮まる力」を広げていく。その風景が、この国に満ちてほしい。

60を越えてからでも、いい人間になろうとすれば、いいのです。
そこで気づけば、遺伝子がオンになってくれたら、「遅い」とか「早い」とか、そういうことじゃない。
一生のうちに、どこかで「開眼」する。置き去りにしてきた「時間」が、確実に戻ってくる。
自分が、自分になれるチャンスが巡ってきた。そう思えばいい。
後悔し、反省する「男たち」は、幼児たちとは、相性がいい。いつまで経っても、中身は子どもなのだから、お互いに、求め合う。
孫の顔を見ると、どれほど自分が、馬鹿げた失敗をしたかが、わかる。(人もいる。😀)特に、男の子は、気の合うお爺ちゃんがいると、良く育つ。
人間は、いつか、いい人になればいい。
追伸:
雇用主が、社員の家庭の安心を手助けし、「逝きし世の面影」にあった、今では失われた「村社会」の絆を、復活する方向に動いてくれたら、まだこの国には、改善できる余地が、大いにある。
保育園や幼稚園で「祖父母の保育士体験」をやり、会社が、職場での人間関係を「優しさが育つ環境」へと、改革してほしい。それができる国であることに、まず感謝しなければ、と思います。