先月、インドのシャクティーセンターにシスター・チャンドラを訪ねた時のこと。
「シスター?チャンドラとシャクティの踊り手たち」から、映像のメッセージ。
オープニング http://youtu.be/YXk7xexQR8I
セルバの結婚観 http://youtu.be/h3OpPP_JY_g
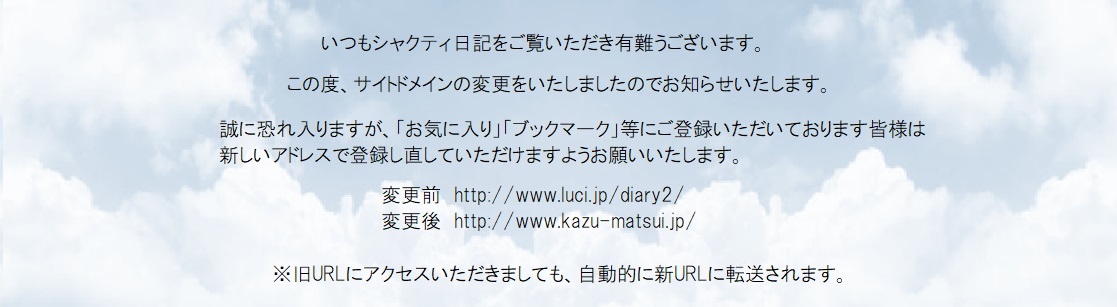
先月、インドのシャクティーセンターにシスター・チャンドラを訪ねた時のこと。
「シスター?チャンドラとシャクティの踊り手たち」から、映像のメッセージ。
オープニング http://youtu.be/YXk7xexQR8I
セルバの結婚観 http://youtu.be/h3OpPP_JY_g
1歳3ヶ月くらいで、息子がお辞儀を覚えた時のこと。
いつもやってくれるわけではないけれど、やってくれるととても優雅で、いい感じです。私しか見ていないと、もったいない気がするのです。見損なった人には、ぜひ見せたくなるのです。もう、それは、平和や美や真実を、わかちあいたい、という感じです。
親子関係にハッピーエンドなんてない。お墓とか、記憶とか、形見とかに体現される、魂の次元のコミュニケーションが存在しなければ。
赤ん坊が、数年かけて左脳である言語脳を発達させている時に、親は赤ん坊という特殊な存在と付き合い、感性を発達させている。祖父母に、より感性が必要な理由…。
幼児との体験が不足し、社会的に感性が欠如している団塊の男たちが、…。
人間たちの出会いの中で、親子の出会いほど決定的で不思議なものはない。一生をかけての出会いである。春夏秋冬を受け入れるように、これを通り抜けて、自然(Nature)と一体になる。その出会いには選択肢がない。そこで人間は運命という言葉を意識するようになる。
人間はいま、選択肢があることに苦しんでいる。
幼児と過ごした記憶を強く持つことは、人間の感性とコミュニケーション能力を高め、その幼児の発達を見て、現実が過去と未来を含むものだと意識する。
音楽が存在するように、
「そんな中でも春はきました。
大変なことばかりを数え上げるときりがないですが、今の私にできることは子ども達を元気にすることだと思って毎日を過ごしてます。
保育士としては当たり前のことですが、それが大人を元気にし、長い目で見れば復興につながるのでは‥と勝手に解釈してるところです。」
たぶん、こういう時だから子どもを眺めて大人たちが癒されるのだと思います。
子どもたちの明るい声や、笑顔に励まされ、この子たちのために、と立ち上がる、考える、絆を作る、それが直接的な日々の幸せになってゆくのだと思います。
遊んでいる子どもたちを眺めること、それが何千年もやっていた癒しでありリハビリテーションなのだと思います。