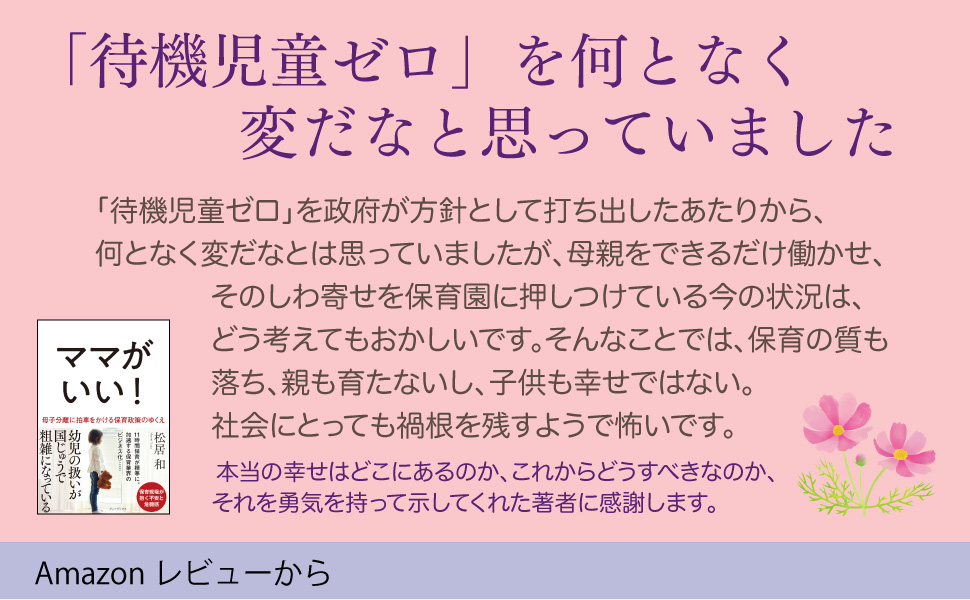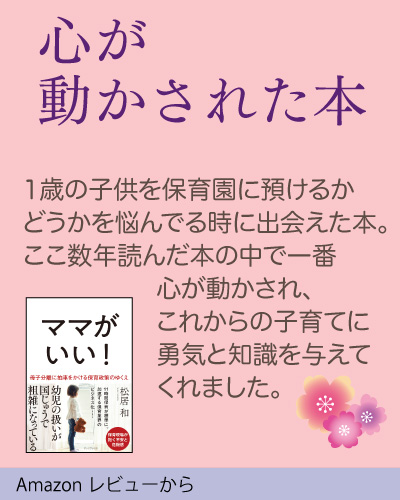松居和チャンネル 第87回は、(テーマが)「保育園、幼稚園の選び方」
副題として、園長の考え方の「格差」が広がっている、としました。
親たちの、「保育園、幼稚園の選び方」によって、将来、子どもたちの努力では、埋められない「格差」が生まれている。
どの園を選ぶかで、親子の、人生が大きく変わる。
子どもの将来の幸せを願って、自分たちは、5歳までしか見れないのだから、と、親たちの覚悟が育つことを重視する園長がいる一方で、政府が言う「保育のサービス産業化」に従って、母子分離に違和感を感じなくなっている園長もいる。(生き残りを賭けて、「理想論を言ってはいられない」と言い切る人もいる。)
保育の基本は、担任の人間性、つまり当たり外れなのですが、やはり、園長の考え方の「格差」が様々な方針に影響する。
その根っこに、「保育士不足」で、園長が、人間性で保育士を選べなくなってきている、という現実があるのです。
質を、整えられない。
政府が作った、この「制度の崩壊」は、養成校の定員割れという状況を考えれば、もはや修復不可能。できるだけ、親に、返していくしかないのです。
母子分離に基づく「雇用労働施策」、そして、保育学者の「専門家に任せればいい。大丈夫」という誤魔化しが、このような状態を生んだのです。
厚労省に、「雇用均等・児童家庭局」というのがあって、その名称が、政府の保育政策を象徴しています。雇用均等(平等ではなく)のための、児童家庭局なのです。
そこの女性局長に、私の言っていることは、「性的役割分担の押し付けではないでしょうか」と言われたことがあります。
「性的役割分担」がなかったら、人類は成り立たない。子育てを楽しむ、意味もない。
今回の、「園を選ぶ基準」ですが、こうなってくれたら、日本は大丈夫かな、という私の強い「希望」です。
もう、これしかない、と思っています。
ーーーーー
#保育 #子育て #母子分離