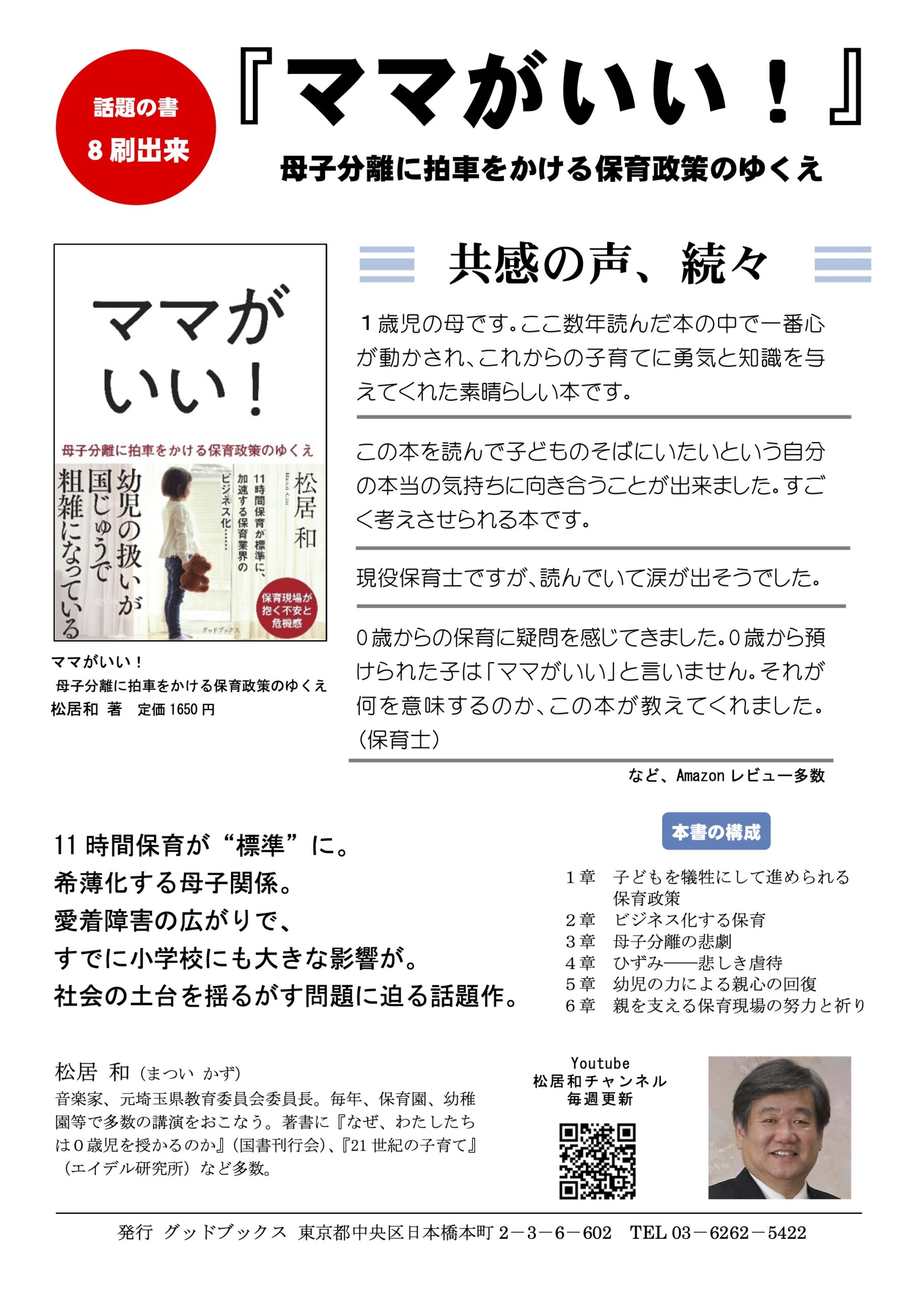子は鎹(かすがい)ではなく、「子育てが、社会の、鎹(かすがい)」だった。これは、労使関係も含めて、なのです。
雇用者も、子育ての重要な一部を担っている。子どもを持つ家庭に「配慮」し、「村(むら)社会的」絆を、維持する。それを、「会社」という仕組みの中で、取り戻す役割を果たさないと、「子育ての負債」は、やがて「従業員の質」という形で、雇用側に、必ず返ってくる。
それを、7時から学校を開けば、悩みがなくなる、などと考えるのは、本当に馬鹿げている。悩みは無ければいけない。それが、人間を育て、人間関係を形作る。
大人たちの利便性のために、子どもの気持ちが無視されている。
保育学者の言う、「専門性」は、結局、「無資格」でいい、「短時間勤務でつないでいい」という規制緩和に繋がっただけです。乳幼児の日々を犠牲にし、「欧米ではこうで」と言って、学者たちが、守ろうとした「保育学」は、保育学科の定員割れ、専門学校の閉鎖という結末を招いている。
日本人は、学問で子育てをしない。三歳児神話と祈りで、子どもを守るのです。