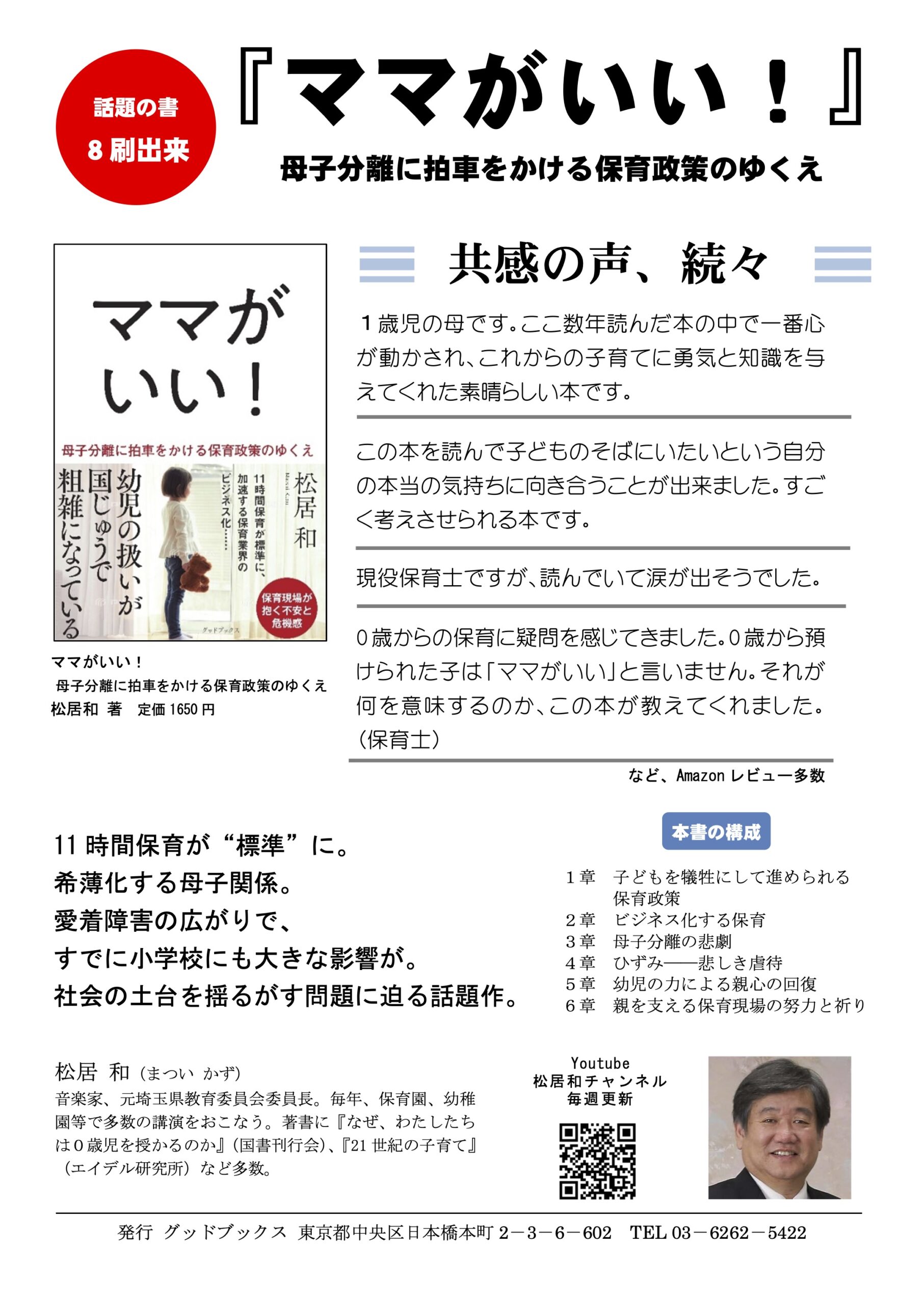松居和チャンネル 第80回のテーマは、11年前に、すでに、心がバラバラだった、という話。子どもを世話してもらいながら、保育料や給食費を払おうとしない親たちが、すでにいた。
お金のやり取りで、子育てを考える「制度」を国が作り、保育者と保護者の心が一つにならなくなっていった。保育を「市場」と考える閣議決定がされ、「業者」が入ってきた。
しかし、
副題は、「明日も来る」という制約の中で、出来ること、としました。
もう一度「子どもを可愛がる」ことで、この国に「美しさ」を取り戻すとしたら、「毎日、子どもが通ってくる」という条件の中で、親心を耕していくしかない。日々の生活が、体験となり、知識や情報に縛られた「関係」から解き放たれる。
選挙とか、SNS上の「言い争い」で、先の見えない無駄な「対立」に引き込まれてはいけない。
この国は、まだ、鎮まっている。
まだ、なんとなく。
子どもが生まれた時に、父親が、家庭に存在する確率が奇跡的に高いのです。
それが、一度失うと、戻せない、先人たちが残してくれた、この国の、自然治癒力。
女性の収監者数もアメリカの100分の1。
保育士さんたちの相談に乗る立場の人から、こんなメールが届きました。
「子どもを抱かないで、と言われる事への辛さを言われる方がいます。
一人の保育士が抱くと他の保育士も抱っこしないといけなくなるから、と言う理由だそうです。
愛着形成のこの時期に、そんな事を言うなんて。
それが何件もあるので、子どもの育ちに胸を痛めます。」
(ここから私)
ここが、闘いの最前線なのです。
子育てを、仕組みに任せておくと、「動機」が曖昧にされ、社会から「信頼」が消えていく。
その一番恐ろしい形が、3歳までの子どもたちの「脳の発達」が、親たちが知らないうちに、阻害されていること。
そんな中で育った子どもたちが教師や保育士になっていること。
経済が良くなって「手取り」が増えても、「国防」を叫んでも、親たちから「子育て」の責任を奪っていく「政策」を続けていては、この国も、分断と、利権争いに明け暮れる欧米の二の舞になってしまう。
親子は、明日も、保育園に来る。
「明日も来る」という環境の中で、保育士たちが「親身になって」頑張れば、道筋は、まだ残されている。「カウンセラーや心理士、専門家」ではできない、日々の尊い、仕事が、そこにある。
「人柄」で会話をする、余地が、再び生まれてきますように、どうぞ、よろしくお願いいたします。