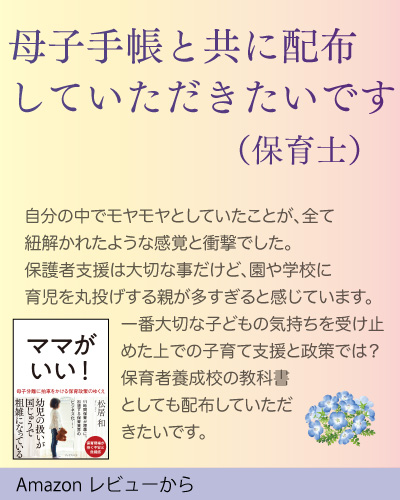毎週、火曜日更新の、「松居和チャンネル」。
引き続き「特別編」を座談会形式で、4回分収録した、その第2回です。
大田区での幼稚園の保護者向け講演会をきっかけに、勉強会をママ友たちと開いてくださっている、まどかさんに司会をお願いし、ゲストも、選んでいただきました。
大田区議会議員の、伊藤つばさ、さん、子育てサロン「ぶーぶーばんぶー」を主宰する、なみえさん、と私の四人で、「ママがいい!」に書かれていることを中心に、様々に、語り合いました。
「〇、一歳児に使っている税金を『直接給付』という形で親に渡し、孤立化を避けるために保育園や児童館に併設した子育て支援センターに週三回ほど午前中だけでも通ってもらうような仕組みを作れば、もともと預けるつもりではなかった親たちを含め、月々七万円くらいは出せる。」つまり、経済的理由で預ける、という論旨は、実は、税収という面では、成り立っていない。
コロナの時に、どうやって「園の行事」や「常識の伝承」が途切れてしまったか、についても話しました。
そして、共働きの習慣が広まると、男たちが「家庭」から逃げる、という私の危惧で、今回は、締めくくったのです。
「稼いでくる」だけでもいいから、男たちを、子育ての責任から逃さないようにしないと、日本も、欧米社会のように、父親が責任を持たない社会になってしまう。そのためには、子育ての責任ではなく、子育ての喜びを、幼稚園、保育園で、父親たちに学んでもらいたい。
「ママがいい!」をテーマに、幼児たちの願いを叶えるべく、チャンネルは、試行錯誤を繰り返し、続いていきます。
「ショート動画」共々、どうぞ、よろしくお願いします 松居 和
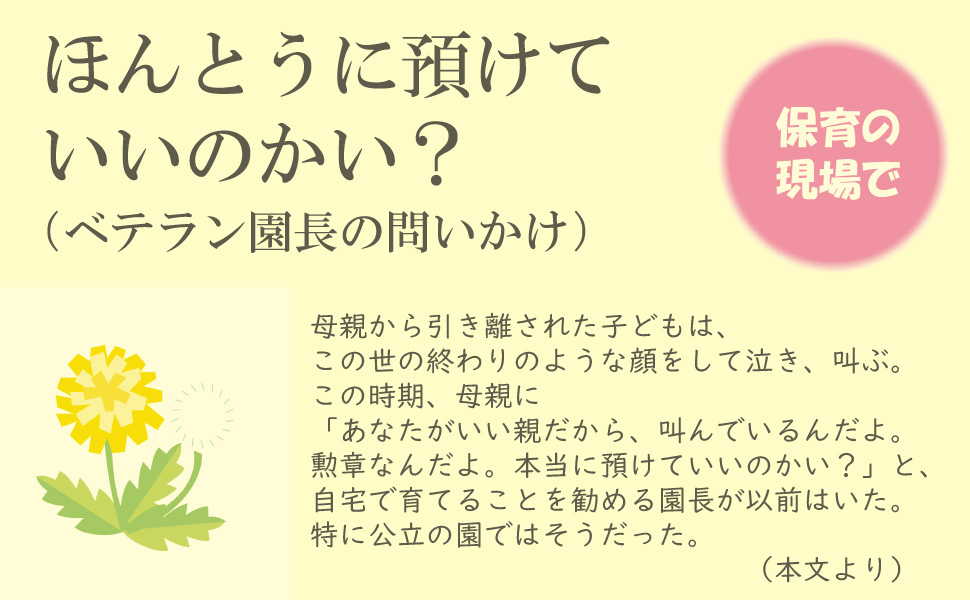
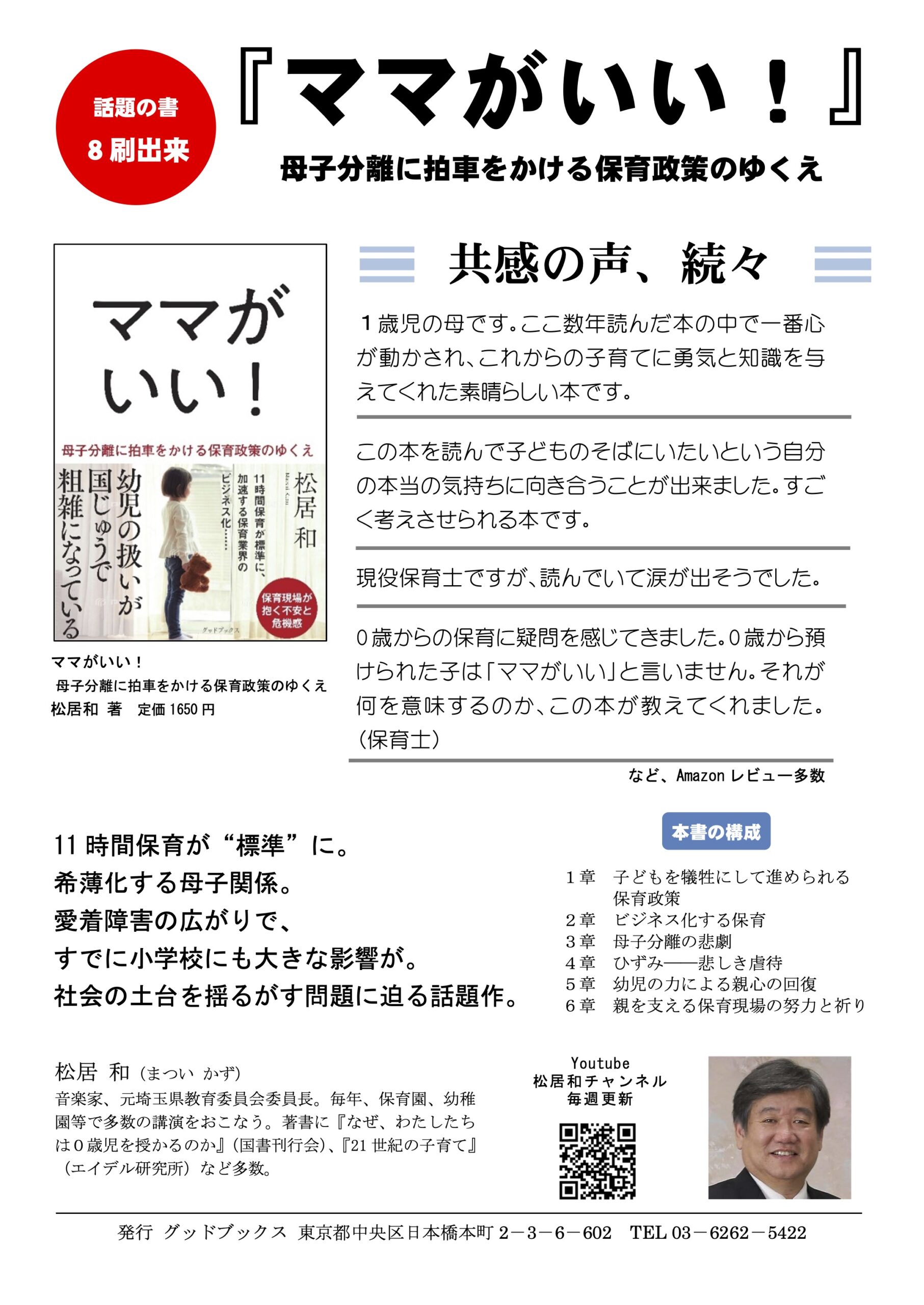
「ママがいい!」を、母子手帳と一緒に配布してほしい、保育者の養成校で教科書として使って欲しい、というAmazonのレビュー。
保育学者たちは、政府の言い成り、母子分離の正当化をしてきたことへの現場からの怒りです。
11時間保育を『標準』としてはいけなかった。「短時間勤務保育士活躍促進」などという誤魔化しの名前を使って、保育士不足を誤魔化してはいけなかった。幼児たちは、1日に二度も交代する保育士の、誰と愛着関係を作るのか、わからないまま日々を過ごしている。そして、学校へ上がっていく。