欧米を追いかける「家庭崩壊」がこの国でも始まっています。だからこそ、保育士や教師という仕事は大切で、やり甲斐のある仕事で、頑張ってほしい。この人たちの幸せを必死に支えなければいけない。それには、「あんたの子だろ」と、必要な時に園長が親に言える雰囲気を、現場に残しておかなければいけない。
募集しても倍率が出ない、保育士の給料がすべての職種の平均より月10万円も低いなどという仕組みでは到底無理だということを、まず、最初に親たちが認識して欲しい。
衆議院調査局「RESEARCH BUREAU 論究第16号に少し丁寧に書きました。ぜひ、読んでください。
本来、非認知能力が育つ土壌は、子どもの周りで生きている人々が心を一つにして、「可愛がる」という風景であって、子どもを拝み、楽しみながら受け継がれていくものでした。それを、学問が壊そうとしている。
私が以前インドで見た風景が、今でも語りかけてくるのです。
親が子どもの幸せを願い、子どもが親の願いをかなえようとする、それが世代を超えて、糸車のように回っていく。
私の作ったドキュメンタリー映画からです。
この風景を見て、貧しい村人の親子の「持参金」をめぐる発言を、無教養だから、教育を受けていないから、と言う人もいるでしょう。
それは確かにそうでしょう。しかし、学問よりも深く、より単純な法則がそこにはあって、DNAの中に仕組まれた伝承の力が「子育て」を柱に、その法則をつないできた。これを忘れるとすべての制度や仕組みが人間性(非認知能力)を失っていくのだ、ということも事実です。
「いい人」とは? と言う問いかけが残ります。
キリスト教では「愛にあふれた人」と言い、仏教では「慈悲深い人」という言い方になるのでしょうか。普通の人、ふつうの親、ということです。
(このドキュメンタリーの上映会をご希望の方は、matsuikazu6@gmail.comまで、ご連絡ください。無料です。)
「ママがいい!」、再び、Amazonのジャンル別1位になっています。
ぜひ、ぜひ、周りの方たちに、一読するよう、薦めて下さい。この国を、子どもたちのために、守らなければ。
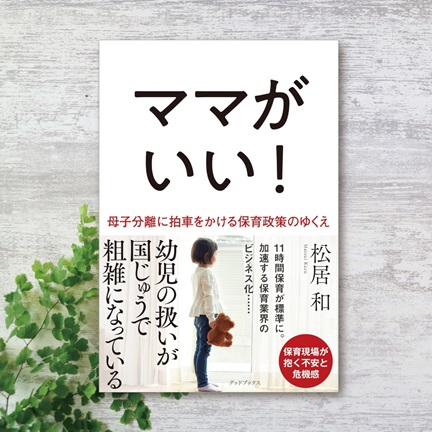
欧米の家庭崩壊に関しては以下のリンクを参照にしてください。
http://kazu-matsui.jp/diary2/?p=1413 (捨てられる養子たち)
http://kazu-matsui.jp/diary2/?p=1428 (米国におけるクラック児・胎児性機能障害(FAS)と学級崩壊)
衆議院調査局「RESEARCH BUREAU 論究第16号 2019.12」
