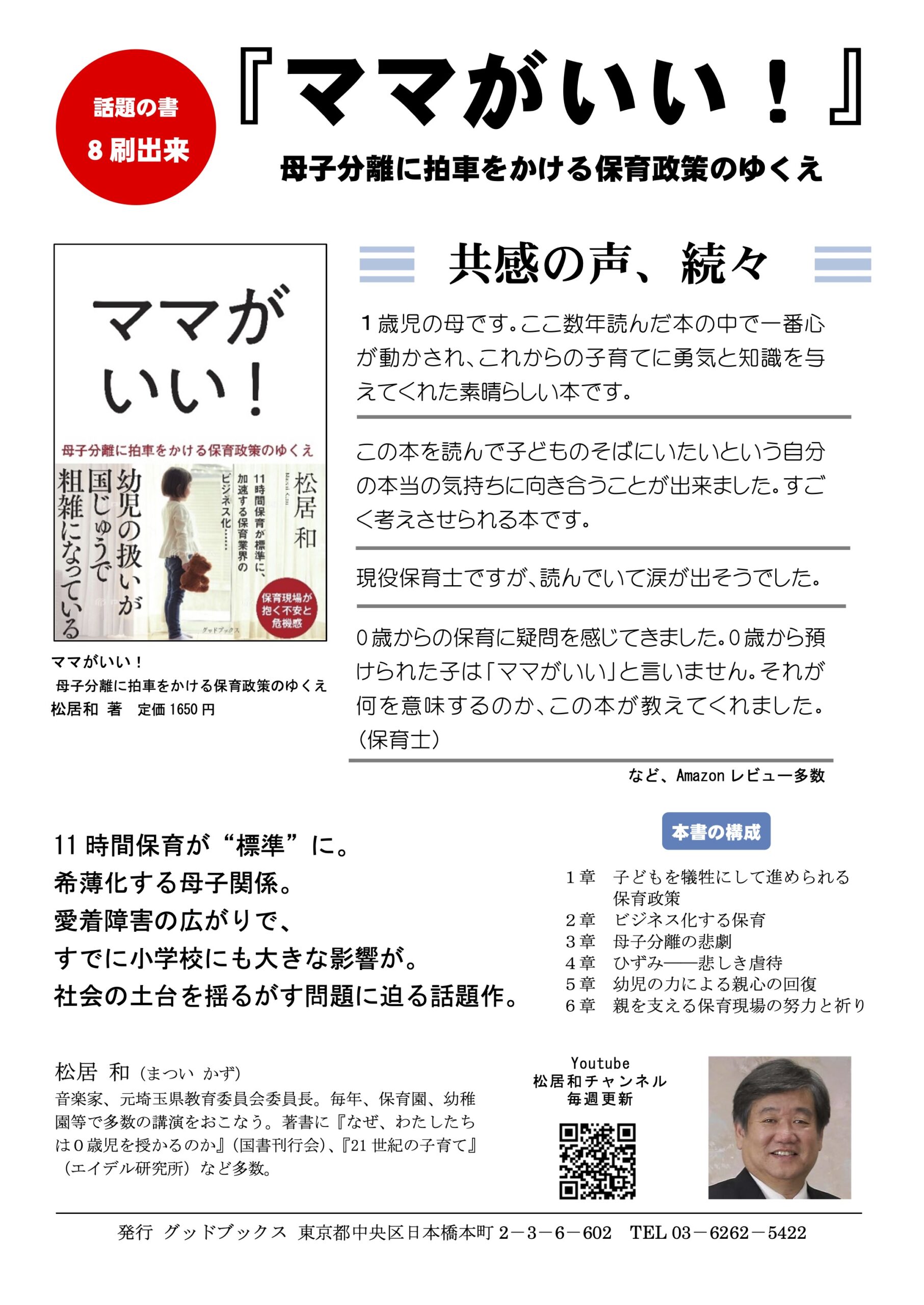松居和チャンネル 第65回(テーマは)「ママがいい!」って、国連さえ言っていた。
そして、副題は:A.I. 対「学問」、にしました。
A.I.に「三歳未満児保育の賛否を尋ねると」、こんな答えが返ってきました。(全文はチャンネルに)
『3歳未満児保育が子どもの発達に与える影響は、保育施設の質や家庭環境との組み合わせ、子どもの個性などにより異なります。(中略)もし保育を選択する場合には、施設の見学やスタッフとのコミュニケーションを通じて「安心して預けられる」と実感できる環境かどうかをしっかり確認することが望ましいでしょう。』
A.I.でさえ「しっかり確認することが望ましい」と言っている。
前回のテーマにした東北大の研究、「発達に悪影響はないので安心して預けてほしい」などと、安易に無責任なことは、言わない。
A.I.ですから、この問題で失敗し、家庭崩壊が日常になってしまった「欧米諸国の研究」を参考にしているのでしょう。これが、人類が、とりあえず行き着いた「グローバルスタンダード」と言ってもいい。
女性の社会進出が常識になっている欧米でさえ、「『安心して預けられる』と実感できる環境かどうか、注意して、確認して」と示唆している。
三歳未満から「安心して預けろ」という研究発表に携わった東北大の学生たちに、言いたいのです。保育界の現場を知っているのか、調べたのか、と。
市場原理に取り込まれ、政府の母子分離政策を手伝うより、破綻寸前の学校教育から、なぜ教師たちが去っていくか、考えて欲しい。研究すべき「流れ」と「現実」は、そちらの方にある。
これを担当した教授が既に決めているであろう、「安心して、預けろ」の、「安心」は究極のグレーゾーンであって、「誰の安心?」かさえ、定かでない。その現実を、「発達」という言葉を使って誤魔化し、保育を歪曲化している。
(チャンネル第59回『一人の、正直な「学者」』ぜひ、ご覧下さい。)

「経済論」では見えない「本質」」が、保育室にはある。こういう研究、発信をするなら、三時間でいい、そこで過ごしてみてほしい。三歳未満児が、何を探しているのか、自分の人間性で、見極めてほしい。
どこの保育科も定員割れを起こし、養成校が次々に潰れていく。なぜ、そうした仕組みの「根っこ」が崩れようとしているかが見えてくるはず。
保育士たちは、ずっと政府の母子分離政策に「違和感」を感じてきたのです。それが、最近ますます強くなっているのは、こういう国立大学の研究、それを後押しするマスコミ報道を鵜呑みにし、「気楽に、預ける親たち」「後ろめたさを感じない親たち」が増えてきたから。
国連さえ言っている「子どもたちの権利」が、隅に押しやられ、誰でも、預けられること」が、「子育て安心」(プラン)だと、政府は、言うのです。
その矛盾した論理に、なぜ、マスコミや保育学者が抵抗しないのか。
心ある保育士たちは、ここまで頑張ってきた。
それが、限界を越えようとしている。
意識改革が、必要です。