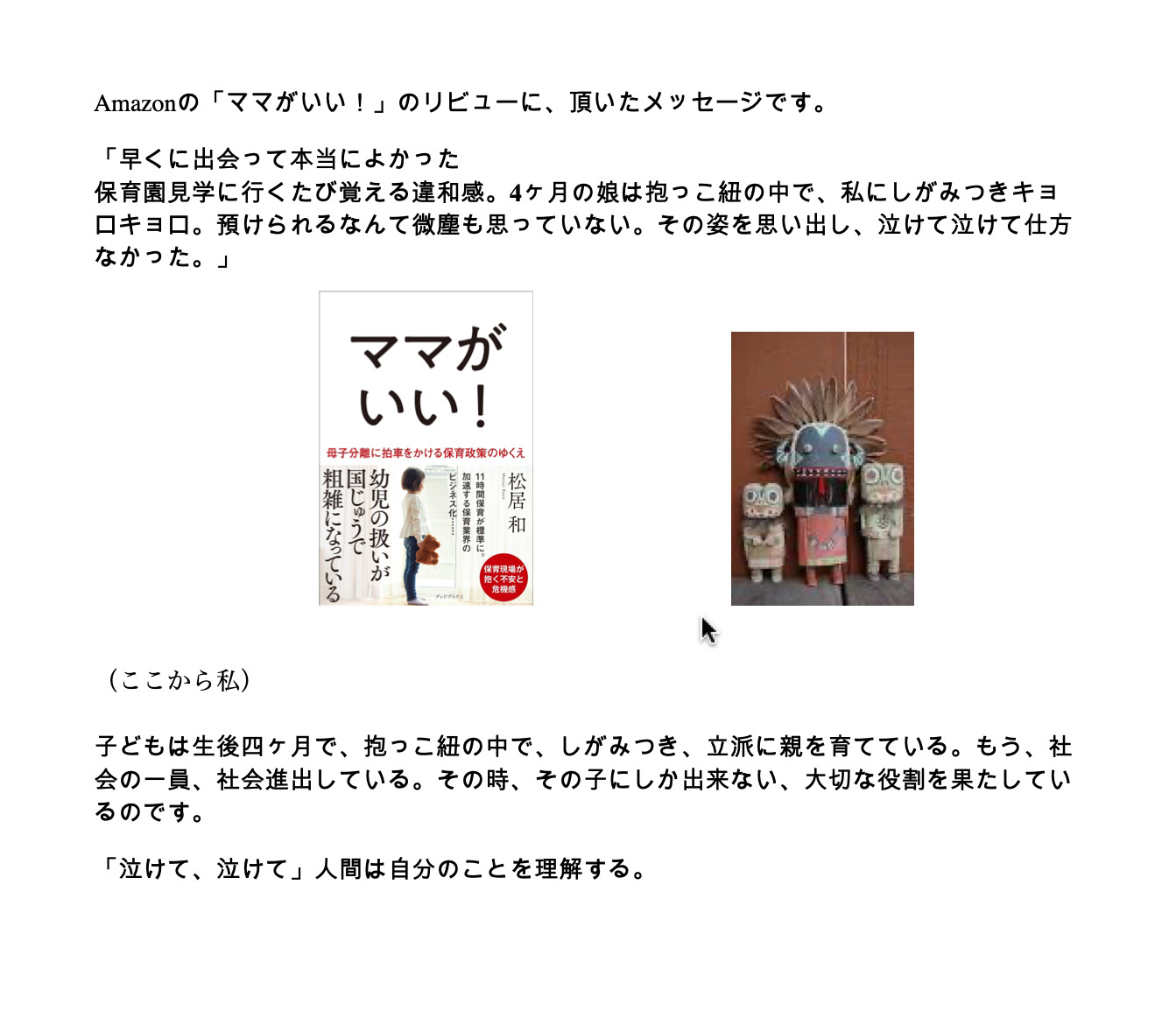▼松居和チャンネル、第64回のテーマは、「選択的夫婦別姓について」。副題は、「対立の時代」、「分断の時代」、としました。
冒頭、いきなりsayaさんに、「聞いてみたい、ことがあったので」と言われ、「選択的夫婦別姓、について。親にとっては『選択的』だけども、子どもにとっては、強制的じゃないか、と反対している方が多い。子どもが大きくなった時に、家族の一体感はどうなのか。戸籍を廃止する動きにつながってくるのではないか。」と訊かれました。
夫婦別姓問題に関しては、家族の崩壊につながる「確率が高まる」ことだと思います。それが、すでに進んでいる家庭崩壊の流れに拍車をかける、それは、避けたい。
その思いが、まず第一。
しかし、「男女平等とか、民主主義という理念があって、その『理念』をどこまで通すのがいいのか。
そのあたりから、根深い「対立と分断」が起こっている。
私は、012歳が安心して、安定した『時』を過ごせること、それを、社会の動きを考える、第一の視点にしています。
『子どもの最善の利益を優先する』という、(これは、人類存続の第一条件)子どもの権利条約に書いてあることが、物差しの根本なのです」。そうsayaさんに答えて、対談が始まりました。
私にとっては、「夫婦別姓問題」は、所詮大人たちの「権利意識と、生活スタイルにおける都合、「選択肢」の問題なのです。
大人たちにとっては、「選択できる」こと。
「012歳を、母親から引き離すこと」とは、次元が違う。
母子分離は、子どもたちの側に選択肢がない。喋れないのですから。だからこそ、ルールは、何万年も守られてきた。その、人類の進化の条件が、突然、ないがしろにされているのです。
絶対に逃れられない「性的役割分担」を不平等であるとして、利権争いの場に引き出せば、「闘う意識」が争点そのものになっていく。分断の「力」が、増すばかり。「法的な問題」を象徴的な事例で争うことで、「人間としての優しさ」「許容力」が消えていく。その方が心配です。
欧米がそうだった。性的役割分担を否定して、「平等」というものに近づけようとしても、潜在的、絶対的な無理、矛盾がある。それは確かに、家庭崩壊につながっていった。しかも、それは許さない、という位置に、いま、回教徒たちがいる。
そんなことも話しました。
私の発言が、正しいというわけではありません。こういう視点がある、ということを、理解していただくことを願うしかありません。最近の「分断と対立」を求める動きは異常です。012歳という、仲裁者の存在意義が弱くなっているからです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。