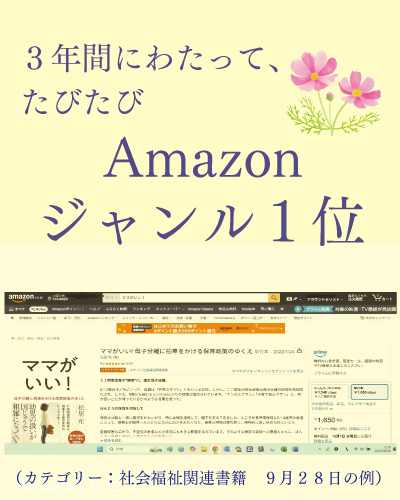松居和チャンネル第93回は、
(テーマ) 国連、子どもの権利宣言
副題: 幼児は、例外的 な場合を除き、その母から引き離されてはならない。
六十年前に、今の「子どもの権利条約」の前身として国連で採択された、「子どもの人権宣言」、
「幼児は、例外的 な場合を除き、その母から引き離されてはならない」と、ハッキリ書かれていた。
3歳児神話は、当時から国連で採択される「グロー バルスタンダード」だった。そこから、なぜ、「母」という言葉が消されたのか。大人の「利権争い」が、「人間性」に取って代わろうとしていたのです。
結果起こった「家庭崩壊」の流れが、今、全世界で、学校教育と福祉を追い詰めている。
「母」という言葉から目を逸らして、人類は成り立たない。そんな中、日本という、欧米に比べれば、まだまだ素晴らしい国で、こんなメールが、保育士からくるのです。
「正直、可哀想すぎて胸がつぶれます。早期から母子分離という虐待のお手伝いをするために国家資格を取ったわけじゃないのにな。預けなくて済む、ありっ たけを考えてやれよ」
一方で、保育学者に影響された「業者」から、「母子分離を可哀想、と思う人は、保育士には向かない」という指摘が来る。
そう、この「保育」という新しい、不自然な「やり方」は、人間には向いていない。だから、自然な反応として、保育士や教師の「成り手」がいなくなる。倍率が出ないと、連鎖反応のように質が下がっていく。
子どもたちの「ママがいい!」という叫びが、不登校という形で「過去最多」になっています。
引きこもりも、過去最多、その平均年齢が40歳を超えている。すでに、それだけの時間が過ぎたのです。
「ママがいい!」という、子どもたちの願い、主張を、政府や保育学者たちは、いまこそ、心を込めて受け止めてほしい。できることは確実にある。「ママがいい!」に書きました。すでにやっている自治体もある。最近の、保育士による不適切保育の実態報道を見ればわかるでしょう。これ以上言い訳や、誤魔化しは通用しない。待ったなしの状況なのです。
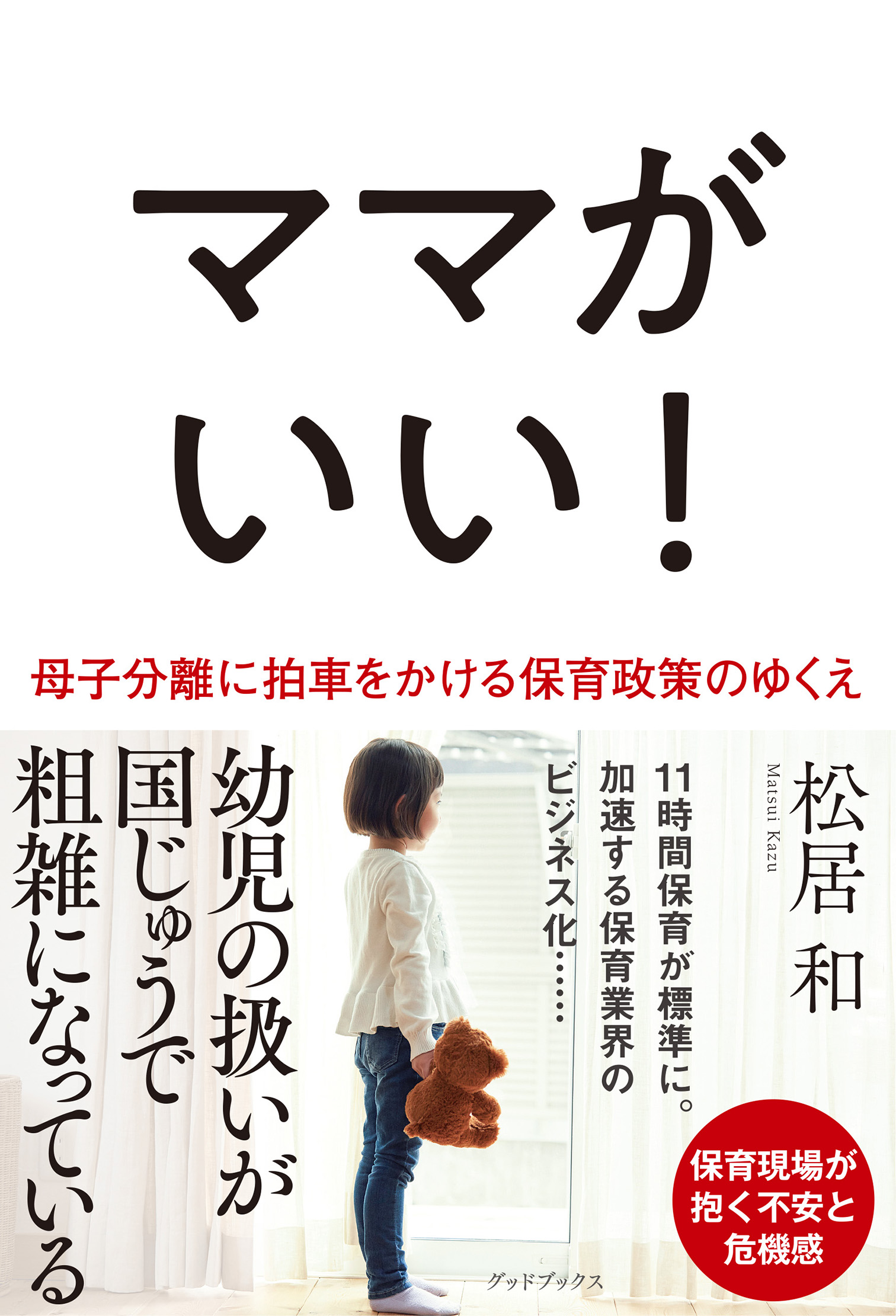
一日保育士体験、そこからです。
保育園に、お父さん、お母さんが来ると、とにかく「子どもが喜ぶ」。その駆け引きのない「自慢げな」心が、仕組みにもう一度「魂」を与える。
いつでも、親に見せられる保育をする。この「常識」を取り戻さないと、保育界はやがて崩壊する。
素晴らしい園長先生との出会いが、親子、一家の人生を変えます。そういう園長先生を、親たち、みんなで大事にしてほしい。「園」を故郷(ふるさと)にしてほしい。
「ママがいい!」、ぜひ、読んでみて下さい。今週も、Amazonの福祉部門、第一位です。
#保育 #子育て #母子分離 #松居和 #ママがいい #こども家庭庁