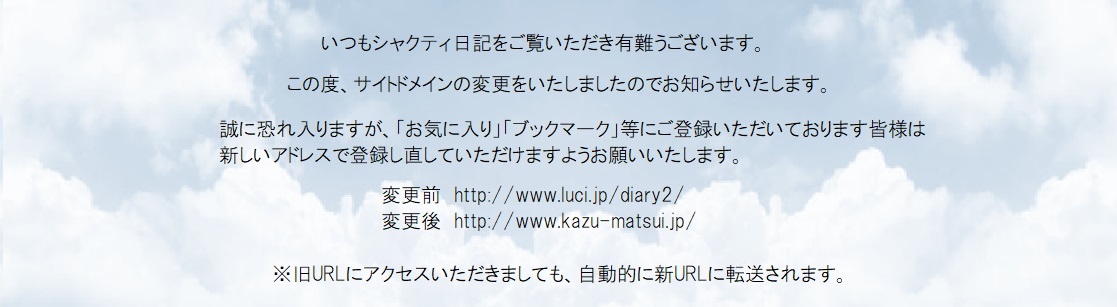先月13日の読売新聞夕刊に、去年逝った、父の遺品と言葉が載っていました。
「母親が自分に読んでくれると言うのは、子どもにとって最高のことです。」(「私の言葉体験」から)
妹、「わにわに」の小風さちさんが、「人形に、幼い頃の自分と母親を重ねていたのかもしれません」とコメントしていました。
絵本も、児童文学もそうですが、何度も何度も読んでもらえる、繰り返し読めるのは、それが「体験」だからです。情報だとしたら、一度でだいたい覚えてしまうし、話の筋も、会話も知っている。
何度も読めるのは、生きた「体験」だからなのです。
私も、ドリトル先生などは、一冊につき5、6回は読みました。「秘密の湖」のあの神秘的、哲学的深さは、いまでも肌触りとして残っています。長靴下のピッピもそうですし、「飛ぶ教室」「太陽の戦士」「農場の少年」「トムは真夜中の庭で」「カラスが池の魔女」、私が思考する中核に、繰り返し読んだ児童文学の体験がはっきりとあります。
児童文学をたくさん読んでいれば、大人の誤魔化しには騙されない、そんな感じです。
アインシュタインが、情報は知識ではない、体験が知識なのだ、と言いました。わかる気がする。
その体験の根っこに、母親に読んでもらう(もちろん父親でもいいのですが)読み聞かせの体験があって欲しい、と父は思っていたのです。
こういう時代だからこそ、もう一度「読み聞かせ」を復活させてほしい。幼稚園、保育園で、親たちに薦めて欲しい。「一日一冊読んであげても、十分くらい。それが母親の言葉として記憶に残っていくんですよ」と教えてあげてほしい。それを、毎日積み重ねていくと、親子でした「体験」の土台が作られていく。こんなに便利な「道具」はないのです。
この時期の体験は、この時期しかできない体験です。お母さん、お父さんも新米で、子どもは、もうキラキラして親を信じている。そういう時に、人間社会の基本が出来上がっていくのです。