子ども中心に生きていた日本人。その様子を見て、欧米人がこの国をパラダイスと呼ぶ。大人が子どもを崇拝し、神々の次元に降りて来て一緒に遊ぶ。自分の中に、3才だった頃の自分、4才だった頃の自分が居ることを確認し安心する。自分が以前神だったことを憶い出し、人間は生きてゆく。
そして、百五十年前にこの国を見た欧米人が、私たちに時空を超えて話しかけてくる。これが、人間のコミュニケーション能力、時空を越えた育てあいの凄さだと思う。

「逝きし世の面影」渡辺京二著、平凡社からの抜粋です。
第十章「子どもの楽園」から
『私は日本が子供の天国であることをくりかえさざるを得ない。世界中で日本ほど子供が親切に取り扱われ、そして子供のために深い注意が払われる国はない。ニコニコしているところから判断すると、子供達は朝から晩まで幸福であるらしい(モース1838〜1925)』
 『私はこれほど自分の子どもに喜びをおぼえる人々を見たことがない。子どもを抱いたり背負ったり、歩くときは手をとり、子どもの遊技を見つめたりそれに加わったり、たえず新しい玩具をくれてやり、野遊びや祭りに連れて行き、子どもがいないとしんから満足することがない。他人の子どもにもそれなりの愛情と注意を注ぐ。父も母も、自分の子に誇りをもっている…(バード)』
『私はこれほど自分の子どもに喜びをおぼえる人々を見たことがない。子どもを抱いたり背負ったり、歩くときは手をとり、子どもの遊技を見つめたりそれに加わったり、たえず新しい玩具をくれてやり、野遊びや祭りに連れて行き、子どもがいないとしんから満足することがない。他人の子どもにもそれなりの愛情と注意を注ぐ。父も母も、自分の子に誇りをもっている…(バード)』
『怒鳴られたり、罰を受けたり、くどくど小言を聞かされたりせずとも、好ましい態度を身につけてゆく』『彼らにそそがれる愛情は、ただただ温かさと平和で彼らを包みこみ、その性格の悪いところを抑え、あらゆる良いところを伸ばすように思われます。日本の子供はけっしておびえから嘘を言ったり、誤ちを隠したりはしません。青天白日のごとく、嬉しいことも悲しいことも隠さず父や母に話し、一緒に喜んだり癒してもらったりするのです』『それでもけっして彼らが甘やかされてだめになることはありません。分別がつくと見なされる歳になると―いずこも六歳から十歳のあいだですが―彼はみずから進んで主君としての位を退き、ただの一日のうちに大人になってしまうのです(フレイザー婦人)』
『十歳から十二歳位の子どもでも、まるで成人した大人のように賢明かつ落着いた態度をとる(ヴェルナー)』
日本について「子どもの楽園」という表現を用いたのはオールコックである。(初代英国公使・幕末日本滞在記著者)
彼は初めて長崎に上陸したとき、「いたるところで半身または全身裸の子供の群れが、つまらぬことでわいわい騒いでいるのにでくわ」してそう感じたのだが、この表現はこののち欧米人訪日者の愛用することとなった。事実日本の市街地は子供であふれかえっていたスエンソン(江戸幕末滞在記著者)によれば日本の子供は「少し大きくなると外へだされ、遊び友達にまじって朝から晩まで通りで転げまわっている」のだった。
ワーグナー著の「日本のユーモア」でも「子供たちの主たる運動場は街上である。・・・子供は交通のことなど少しも構わずに、その遊びに没頭する。彼らは歩行者や、車を引いた人力車夫や、重い荷物を担った運搬夫が、独楽(こま)を踏んだり、羽根突き遊びで羽根の飛ぶのを邪魔したり、凧の糸をみだしたりしないために、少しのまわり路はいとわないことを知っているのである。馬が疾駆して来ても子供たちは、騎馬者や駆者を絶望させうるような落ち着きをもって眺めていて、その遊びに没頭する。」ブスケもこう書いている。「家々の門前では、庶民の子供たちが羽子板で遊んだりまたいろいろな形の凧を揚げており、馬がそれを怖がるので馬の乗り手には大変迷惑である。親たちは子供が自由に飛び回るのにまかせているので、通りは子供でごったがえしている。たえず別当が乳母の足下で子供を両腕で抱き上げ、そっと彼らの戸口の敷居の上におろす」こういう情景は明治二十年代になっても普通であったらしい。彼女が馬車で市中を行くと、先駆けする別当は「道路の中央に安心しきって座っている太った赤ちゃんを抱き上げながらわきえ移したり、耳の遠い老婆を道のかたわらへ丁重に導いたり、じっさい10ヤードごとに人命をひとつずつ救いながらすすむ。」
『ヒロンやフロイスが注目した事実は、オランダ長崎商館の館員たちによっても目に留められずにはおかなかった。ツユンベリは「注目すべきことに、この国ではどこでも子供をむち打つことはほとんどない。子供に対する禁止や不平の言葉は滅多に聞かれないし、家庭でも船でも子供を打つ、叩く、‘殴るといったことはほとんどなかった」と書いている。「船でも」というのは参府旅行中の船旅を言っているのである。またフィツセルも「日本人の性格として、子供の無邪気な行為に対しては寛大すぎるほど寛大で、手で打つことなどとてもできることではないくらいである」と述べている。
このことは彼らのある者の眼には、親としての責任を放棄した放任やあまやかしと映ることがあった。しかし一方、カッテンディーケにはそれがルソー風の自由教育に見えたし、オールコックは「イギリスでは近代教育のために子供から奪われつつあるひとつの美点を、日本の子供たちはもっている」と感じた。「すなわち日本の子供たちは自然の子であり‘かれらの年齢にふさわしい娯楽を十分に楽しみ‘大人ぶることがない」。
オイレンブルク伯は滞日中、池上まで遠乗りに出かけた。池上には有名な本門寺がある。門を開けようとしない僧侶に、つきそいの幕吏が一分銀を渡してやっと見物がかなったが、オイレンブルク一行のあとには何百人という子どもがついて来て、そのうち鐘を鳴らして遊びはじめた。役僧も警吏も、誰もそれをとめないでかえってよろこんでいるらしいのが、彼の印象に残った。
日本人は子どもを打たない。だからオイレンブルクは「子供が転んで痛くした時とか‘私達がばたばたと馬を駆って来た時に怖くて泣くとかいう以外には、子供の泣く声を聞いたことがなかった。
日本の子どもは泣かないというのは、訪日欧米人のいわば定説だった。モースも「赤ん坊が泣き叫ぶのを聞くことはめったになく、私はいままでのところ、母親が赤ん坊に対して癇癪を起しているのを一度も見ていない」と書いている。イザベラ・バードも全く同意見だ。「私は日本の子どもたちがとても好きだ。私はこれまで赤ん坊が泣くのを聞いたことがない。子どもが厄介をかけたり、言うことをきかなかったりするのを見たことがない。英国の母親がおどしたりすかしたりして、子どもをいやいや服従させる技術やおどしかたは知られていないようだ」。
レガメは一八九九(明治三十二)年に再度の訪日を果したが‘神戸のあるフランス人宅に招かれた時のことをこう記している。「デザートのとき‘お嬢さんを寝かせるのにひと騒動。お嬢さんは四人で、当の彼女は一番若く七歳である。『この子を連れて行きなさい』と、日本人の召使に言う。叫ぶ声がする。一瞬後に子供はわめきながら戻ってくる。—–これは夫人の言ったままの言葉だが、日本人は子供を怖がっていて服従させることができない。むしろ彼らは子供を大事にして見捨ててしまう」。つまり日本人メイドは、子どもをいやいや服従させる手練手管を知らなかったのだ。日本の子どもには、親の言いつけをきかずに泣きわめくような習慣はなかった。』
『日本についてすこぶる辛口な本を書いたムンツィンガIも「私は日本人など嫌いなヨーロッパ人を沢山知っている。しかし日本の子供たちに魅了されない西洋人はいない」と言っている。チェンバレンの意見では、「日本人の生活の絵のような美しきを大いに増している」のは「子供たちのかわいらしい行儀作法と、子供たちの元気な遊戯」だった。日本の「赤ん坊は普通とても善良なので、日本を天国にするために、大人を助けているほどである」。モラエスによると、日本の子どもは「世界で一等可愛いい子供」だった。』
『モースが特に嬉しく思ったのは、祭りなどの場で、またそれに限らずいろんな場で大人たちが子どもと一緒になって遊ぶことだった。それに日本の子どもは一人家に置いて行かれることがなかった。「彼らは母親か、より大きな子どもの背中にくくりつけられて、とても愉快に乗り回し、新鮮な空気を吸い、そして行われつつあるすべてを見物する。
ブスケによれば「父とか母が一緒に見世物に行くときは、一人か二人の子どもを背中に背負うか、または人力車の中に入れてつれてゆくのがつねである」。
ネットーの言うところでは「カンガールがその仔をその袋に入れてどこえでもつれて行くように、日本では母親が子どもを、この場合は背中についている袋に入れて一切の家事をしたり、外での娯楽に出かけたりする。
子どもは母親の着物と肌のあいだに栞のようにはさまれ、満足しきってこの被覆の中から覗いている。
その切れ長の目で、この目の小さな主が、身体の熱で温められた隠れ家の中で、どんなに機嫌をよくしているか見て取れることが出来る。」
「ネットーは続ける「日本では、人間のいるところならどこを向いて見ても、その中には必ず、子どもも二、三人はまじっている。母親も、劇場を訪れるときなども、子どもを家に残してゆこうとは思わない。もちろん、彼女はカンガルーの役割を拒否したりしない」
チェンバレンはまた「日本の少女は我々の場合と違って、十七歳から十八歳まで一種のさなぎ状態にいて、それから豪華な衣装をつけてデビューする、というようなことはない。ほんの小さなヨチヨチ歩きの子どもでも、すばらしく華やかな服装をしている。」と言っている。彼は七・五・三の宮参りの衣装にでも目をとめたのであろうか。彼が言いたいのは、日本では女の子は大人の衣装を小さくしたものを着ていると言うことだ。
フレイザーは1890年の雛祭りの日、ある豪族の家に招待されたが、その日のヒロインである五歳の少女は「お人形をご覧になられますでしょうか、別の部屋においでくださる労をおかけしますことをどうかお許し下さい。」と口上を述べ「完璧に落ち着き払って」メアリの手をとっておくの間に導いた。
彼女のその日のいでたちをメアリは次のように描写する。
「彼女は琥珀色の縮緬のを着ていたが、その裾には青に、肩は濃い紫をおび、かわいらしい模様の刺繍が金糸でほどこされ、高貴な緋とと金の帯がしめられていた。頭上につややかに結い上げられた髪は、宝石でちりばめたピンでとめられ、丸いふたつの頬には紅がやや目立って刷かれていた。」
メアリの著書に「私の小さな接待役」とキャプション入りで揚げられている写真を見ると、彼女は裾模様のある振袖の紋服を着、型どおりに右手に扇子を持ち、胸には懐刀を差している。つまりこの五歳の少女は完璧に大人のいでたちだったのである。
しかしそれは服装だけのことではなかった。
イザベラ・バードは明治十一年、日光の入町村で村長の家に滞在中、「公式の子どものパーテイー」がこの家で開かれるのを見た。
主人役の十二歳の少女は化粧して振袖を着、石段のところで「優雅なお辞儀をしながら」やはり同じ振袖姿の客たちを迎えた。
彼女らは「暗くなるまで、非常に静かで礼儀正しい遊戯をして遊んだ」が、
それは葬式、結婚式、宴会といった大人の礼儀のまねごとで、バードは「子どもたちの威厳と落ち着き」にすっかり驚かされてしまった。』
『日本人が子どもを叱ったり罰したりしないというのは実は、少なくとも十六世紀以来のことであったらしい。十六世紀末から十七世紀初頭にかけて、主として長崎に住んでいたイスパニア商人アビラ・ヒロンはこう述べている。「子供は非常に美しくて可愛く、六、七歳で道理をわきまえるほどすぐれた理解をもっている。しかしその良い子供でも、それを父や母に感謝する必要はない。なぜなら父母は子供を罰したり、教育したりしないからである。」。日本人は刀で人の首をはねるのは何とも思わないのに、「子供たちを罰することは残酷だという」。かのフロイスも言う。「われわれの間では普通鞭で打って息子を懲罰する。日本ではそういうことは滅多におこなわれない。ただ言葉によって譴責するだけである」。』
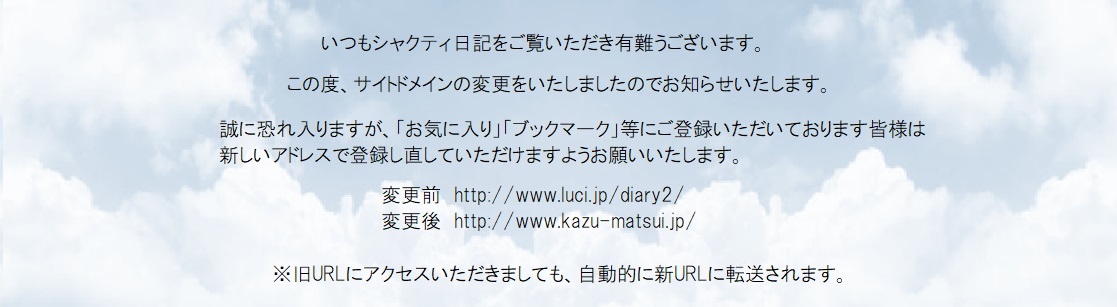
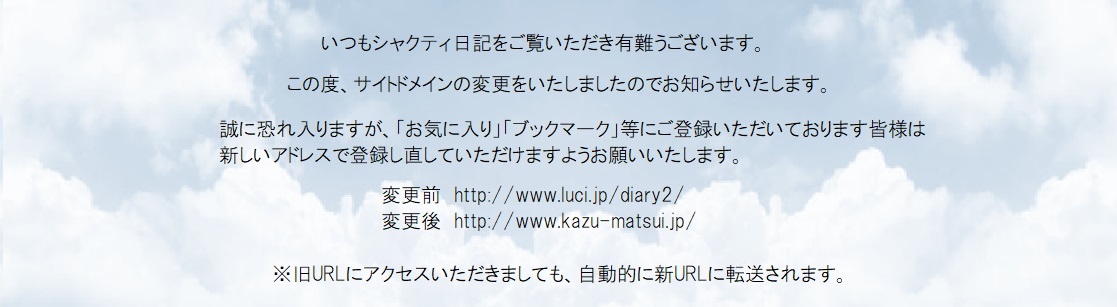

 『私はこれほど自分の子どもに喜びをおぼえる人々を見たことがない。子どもを抱いたり背負ったり、歩くときは手をとり、子どもの遊技を見つめたりそれに加わったり、たえず新しい玩具をくれてやり、野遊びや祭りに連れて行き、子どもがいないとしんから満足することがない。他人の子どもにもそれなりの愛情と注意を注ぐ。父も母も、自分の子に誇りをもっている…(バード)』
『私はこれほど自分の子どもに喜びをおぼえる人々を見たことがない。子どもを抱いたり背負ったり、歩くときは手をとり、子どもの遊技を見つめたりそれに加わったり、たえず新しい玩具をくれてやり、野遊びや祭りに連れて行き、子どもがいないとしんから満足することがない。他人の子どもにもそれなりの愛情と注意を注ぐ。父も母も、自分の子に誇りをもっている…(バード)』