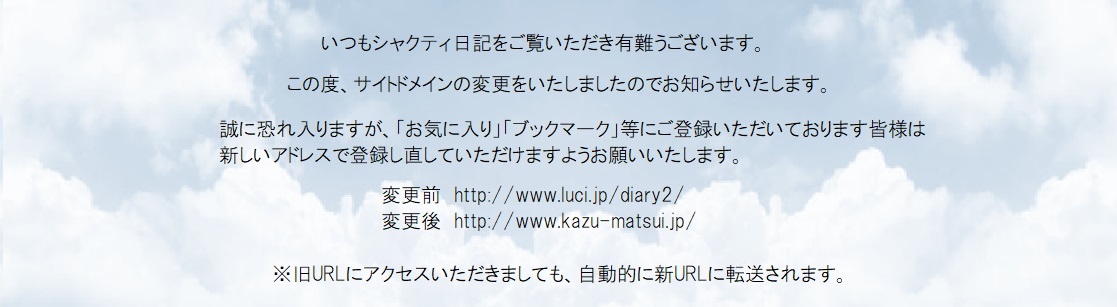2016年8月
ここ数回、ブログに以前著書に書いた文章にいく行か足して、再考し、書いています。いまの日本は、家庭崩壊・学校崩壊という側面から数字的に見ればアメリカの60年くらい前の状況だと思います。だから、20年前に書いた文章が、日本のこの先20年後を暗示しているような感じがするのです。
ホームスクール (学校教育システムの否定)
義務教育があるかぎり、子供たちはある年齢に達すると、親の手を離れ、学校で友達から様々な影響を受けるようになります。良い影響もありますが、当然、悪い影響もあります。義務教育が普及した国では、親の趣味や意志どおりには子育てができ難くなったのです。これは、人類にとって初めての経験です。同年代の子ども達を長期間一緒にすれば、場合によっては、友達から受ける影響の方が、親から受ける影響より強くなっても不思議ではない。年頃になって、そこに恋愛感情が入ればなおさらでしょう。子どもの成長が、家族ではなく、これほど社会状況に影響されるようになったのも、巨大な伝達媒体として機能する「義務教育」が存在するからです。
(義務教育が普及すると子育ての社会化によって家庭が崩壊し始め、それによって義務教育の崩壊が始まる。これは以前にも書いた、私が最初に書いた本のテーマだったのですが、1984年、米国政府は教育の問題を「国家の存続に関わる緊急かつ最重要問題」と定義し一年間大騒ぎしました。義務教育が普及し親の世代に50%だった高校の卒業率が72%になっていたにも拘わらず、子ども達の平均的学力が親のそれを下回った。国の歴史始まって以来初めての出来事でした。目的としたことの反対の結果が出たのです。しかもその年、高卒の非識字率が20%を越えたのです。義務教育や福祉が子育てに関わるようになることによって、「家庭」の機能を弱めてゆく。それに気づいて、うまく対処してゆかないと、経済活動という欲をエネルギーにする勝者の幸福論に引き込まれる。しかし、そのやり方では、一握りの人しか目的を達することができない。しかも、目的を達したとしても、「子育て」の環境が崩れてゆくと、結局幸福にはなれない。)

義務教育が普及してからも、ホームスクールという形で、親が子どもを家庭で教育するやりかたは、常にアメリカ社会に存在してきました。
学校がダーウィンの進化論を教えることが、聖書に書かれているアダムとイヴの話に反するという宗教的理由で公立学校に子どもを通わせない親達の存在は、大統領が聖書に手を置いて宣誓する国で、ある種の賞賛を以て容認されてきました。
1970年に12500人の子どもが、家で親から教育を受けていました。この数字が、1990年には30万人に急増し、それが2000年に150万人、30年間に100倍以上に増えたのです。(この30年間の変化は、児童虐待の数とか、少年犯罪の増加など、様々な変化と連動しています。現在の日本はその数歩手前に居る、と私は考えています。)
1.5%、65人に一人の子どもが学校に行かず、親から学問を学ぶ、これはもはや宗教的理由ではない、親達の学校に対する強烈な不信感を物語っているのです。
自分の子どもに教えるという非常に忍耐力のいる役割を自ら引き受ける、それだけでも相当な覚悟がいるでしょう。共稼ぎが主体になっている社会で、経済的な面を考えても、また、社会進出が当たり前という女性心理から言っても、加えて、シングルペアレントの割合いの多さを考慮しても、これは日本人が考えるよりはるかに大変な数字なのです。ホームスクールをやりたくても出来ない親、そして教育が「義務」であることを考えれば、数字に現われない、潜在的な学校不信は想像以上のものでしょう。
1993年、全ての州で、親に直接子どもを教育する権利が認められました。ほとんどの州で、親の学歴は問われません。親達がホームスクールを選択する主な理由は、30年前は宗教的理由でしたが、いまは子どもの身の安全、親子関係の深まり、望まない交友関係などです。その他特殊事情、例えば学校の授業進行が遅すぎる、早すぎる、身体的事情、精神的事情なども上げられていました。
ホームスクールをより現実的な選択肢に発達させた環境の変化として挙げられるのが、インターネットの普及、公立学校の施設利用が容易になったこと、教則本の発達、小グループの集まりを斡旋するシステムの発達などです。現在、ほとんどの州が、ホームスクーリングコーディネーターを用意し、家庭で子どもを教育したい、学校に子どもを行かせたくない親達の要求に、積極的に答えようとしています。
親達の学校否定の理由の中心が、学校の教育内容に対する不満から、「他の子ども達」という環境問題に移っている。「他の子ども達」は即ち「他の親達」、「他の親達の子育て」です。これは実は、学校の問題ではなく、親同士の問題なのです。学校はこの問題を構造的に生み出した要因であり、広まりを進める媒介役となっていますが、本質的には親達の問題なのです。
当時(20年前)日本で、日教組の教育研究全国集会がテレビで報道されていました。子ども達の代表を招いて意見を聴いたり、学校を魅力的なものにしようと論議していました。アメリカに住み、その現場を知っていた私は、本当に学校が子育てを引き受けちゃっていいのですか、という思いで見ていました。子ども達の要求のほとんどは、本来、人間関係としては、親に求められる種類のものであって、30人40人の子どもを相手に、1人の担任が応えられるものではないように思えたのです。
子どもをこういう討論会に参加させること自体が、私には理解出来ませんでした。その頃、NHKもよく子どもの意見を聞く番組を作っていました。子どもを参加させることで子どもの人権に理解があるのだという姿勢を見せているのでしょう。でも、こんな風に公共の電波を通して子どもに媚びを売っていいのでしょうか。子どもの人格を尊重すると言えば聞こえは良いですが、子どもの背後にいる親達のイメージを切り離していることがすでにとても不自然でした。
番組に出てくる子ども達が自分で働いて、食べているなら構いません。欧米のホームレスの子ども達のように、親に捨てられ、自分で生きようとしている子ども達の発言であれば懸命に聞くべきです。しかし、養ってもらっているのなら、親達も一緒に出すべきです。「ここに居る人に食べさせてもらっています」とお辞儀をして、それから、親の前で喋らせるべきです。それが本来の社会構造だと思います。「養う」「養われる」というのは、平等ではなくても、美しい関係です。それを子どもに意識させる、教えることは大切なのです。番組を見ていて、責任を伴わない空論の中に子ども達を呼び込んで、自分たちの人権意識の高さに酔っている識者たちが、ますます子ども達を甘やかしているように見えました。
「子どもの権利条約」は、それがなくては子どもを守れないほど子どもを囲む環境が悪化している国々の集まりで作られました。「受験戦争は子どもを苦しめている」などと呑気で平和な論争が行われている、世界で一番子どもを囲む環境が良い日本に、この条約を「進歩」の名で持ち込んだら、結局子ども達と人権屋さんを増長させ、個人主義を誤解した子どもが、やがてとんでもない親に育ってゆくのではないか。そんなことをしていたら、「子どもの権利条約」で子ども達を本当に守らなければならない社会に日本もやがてなるのかもしれない、と思いました。今は、「親としての幸福論」を社会から失わない努力をすべきではないでしょうか。欧米に対しては、条約で縛られなければ子どもの幸せが守れないレベルまで、日本はまだ落ちてはいない、と毅然とした態度で言うべきです。それが欧米に対しての日本の役割だと思います。
同じ全国集会で、叱らないで、まず誉める、という研究発表がされていました。叱った方が良い子どももいれば、叱らない方が良い子どももいるでしょう。叱るのが得意な先生もいれば、下手な先生もいるのです。おとなしい先生も、気の弱い先生も、まあまあ授業が出来る「形」を親たちが作る。それが義務教育のルールだと思います。どんな先生でも、まあまあ授業が出来る形を作るために必要なのは、親達の意識と、「形」を守ろうとする社会の厳しさです。おとなしい先生や気の弱い先生との出会いが、子どもの人生に良い影響を及ぼすことだっていくらでもあるのですから。
翌朝の新聞に載った見出しが、「固定観念捨て学校の改革を」です。いまこそ学校が本来の固定観念を再確認し、親達に学校というのは本来こういうものですから、と言わなければいけないのに、泥沼へ自分から入り込んでゆく観がありました。
「生きるちからをつける」なんて抽象論をまた教育要綱で言う。自分の子どもを育てるときに出てこないような言葉を、担任に押しつける、机上の空論もここまで来ると圧巻です。そんなことは私には出来ないと思う親達が、保育者や教師という一見「専門家」のように見える人たちに、ますます子育てを頼るようになるのです。「生きるちからをつける」「自主性」などという言葉を使って、子ども達を野放しにしたら、子ども達の「生きるちから」がますます弱まっていくことがなぜわからなかったのでしょうか。その結果、いま一生に一度も結婚しない男性が3割になろうとしています。
画一教育に順応できる子どもを親が育てないのなら、家庭に突き返すくらいの意志を学校が見せないと、いずれ心ある親達が学校に見切りをつけなければならない時代が、すぐそこまでやってきています。それとも、子育てに関する常識や秩序が崩れつつある今、もう親達に子育てを返すのは無理な社会状況なのでしょうか。それほど、日本の親達の意識の中で、家庭崩壊は進んでしまっているのでしょうか。

第三世界型学校教育
学校教育と家庭の崩壊が一気に進んだ1990年代、中途退学者の急増、校内犯罪の増加、教師の質とモラルの低下など、あらゆる面で学校教育が崩壊寸前の危機に追い込まれていたシカゴで、何でもやってみるしかないという市長の決断で、周囲の反対を押切り、それまで学校の運営とカリキュラムの決定を行っていた教育委員全員を解雇し、教育委員会を解散、それぞれ個々の学校が父母と相談して各学校独自のカリキュラムの作成、運営を行っていく、という試みが実施に移されました。
長年のシステム化に次ぐシステム化によって硬直化してしまった学校教育を小規模に分割することで活性化しようというこの試みを、彼らは自ら、Third World School System(第三世界的-発展途上国的学校システム)と呼びました。ちょっと自虐的な、開き直りともいえるこの動きには、子どもを教育する責任は誰にあるのか、責任を誰がとるのか、教育委員会かなのか、教師なのか、親なのか、子ども自身なのか、という教育の原点をもう一度考え直してみようという、せっぱ詰まった危機感がありました。
カリキュラムの作成を任せ、学校の運営に参加させることによって、親達の役割をより大きなものにして行こうというこの試みは、親達の関心を即す具体策として興味深いものでした。
父母たちは、カリキュラムの作成、学校の運営に関しては素人です。それまで専門家が研究し、行ってきたことを、現場の教師たちとの協議の上とはいえ父母(素人)に任せることが、教育内容や運営の改善につながるとは思えません。しかし、そうした教育内容や運営形態の善し悪しよりも、父母達の目を子ども達に向けることの方が重要だ、とこの市長は考えたわけです。専門家達による様々な改革や試行錯誤の末、どうやってみても親達の関心なくしては学校は成り立たないということが明らかになったため、専門家の集まりである教育委員会の解散という象徴的非常処置をとったのです。
「専門家からの脱皮」ともいえるこの動きは、学校教育の内容よりも、「形」、在り方を重視しようというもので、学校教育システムが人間社会の形態をも変えようとしているいま、注目すべき象徴的試みでした。

ベトナム難民の子どもたち
40年前、私がアメリカに住み始めた時のことです。ロサンゼルスの公立高校を成績優秀者で卒業する子ども達に、ベトナム難民の子どもが異常に多い、という報告がされていました。数年前まで英語も満足に喋れなかった難民の子ども達が、20%の非識字率を出すアメリカの公立学校を、成績優秀で次々に卒業して行くのです。アジア系の子どもは一般に勉強が出来ます。アイビーリーグなどは既に四人に一人がアジア系の学生と言われています。これは別に頭が特別良いわけではなく、家庭がしっかりしているからなのですが、その中でもなぜベトナム難民の子どもに偏ったのか。ベトナム難民の親子は、戦争、難民という辛い体験を親子で乗り越えてきた人達です。親子で苦労したことによって家族の絆が強くなっている。「言葉」というのは人間関係によって質も重さも変わってきます。ベトナム難民の親が言う「勉強しなさい、頑張りなさい」という言葉は、普通の親が言う言葉よりはるかに重みがあるのです。そして、ここでもう一つ見過ごしてはならないのは、子どもが親の言うことをある程度無条件に受け入れる親子関係があれば、アメリカの学校がそのままでも機能する、ということなのです。