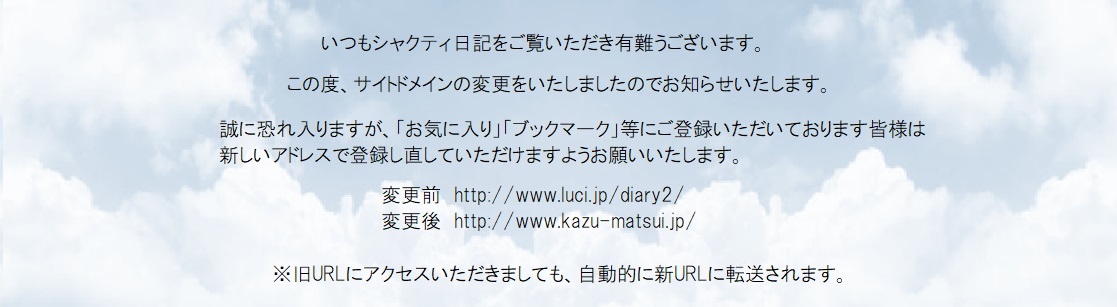40年前、インドで一年間暮らしたときは、様ざまなことを学びました。
インドには巨大なゴキブリがいて、日本から持って行った私の浴衣を食べました。近所のお茶屋さんに相談に行きました。ゴキブリ退治の道具を買いに行ったつもりでした。
そのお茶屋さんが、「ゴキブリに餌をやっているかい?」と私に聞きました。「パンの端っくれでも置いておけば、着物はたべないよ」と言うのです。
こういう答えは新鮮でした。ものさしを変えれば答えは一つではない、そのときどのものさしを選ぶかが人間の生き方なのです。

そのお茶屋さんに三人の息子がいました。五歳、七歳、一〇歳、くらいだったと思います。上の二人はいつも父親を手伝って働いていました。でも、一番下の子は不思議な子で、いつもランプの光をじっと眺めて布にくるまって座っていました。ある日、主人が私に相談したのです。この一番下の息子は変わっている、みんなで相談して「学校」に行かせてみようかと思う、少し支援してくれないか、と言うのです。
学校は変人が行くところ、と気づいたのははじめてでした。私の中で、学校に対するイメージが変わりました。何かが見え始めたのです。とても大事なことを教えてもらった気がして、奨学金を寄付しました。
こういう人間と学校の関係にかかわる話は、昔、学校が普及し始めたころ、どこにでもあったようです。
ローラ・インガルス・ワイルダー(一八六七~一九五七)の書いた『農場の少年』という本があります。ワイルダーは「大草原の小さな家」シリーズで有名です。『農場の少年』もこのシリーズ中の一作ですが、労働と子育ての関係、という視点で読むと勉強になります。「大草原の小さな家」シリーズは、ローラが若くして教師になったこともあり、義務教育が普及し始めた当時の家庭と学校の関係を知るのに参考になる本です。
『農場の少年』の中に、村に新しい先生が赴任してくる話があります。教会を借りた教室で、一人の先生が年齢の異なる子どもたちを教えている開拓時代の学校です。新しい先生が赴任してくると、その先生を年長の子どもたちが殴ったり蹴ったりして追い出そうとする、それを親が奨励する、と書いてあるのです。これは乱暴な話だな、と読み進めると、前にいた先生も殴ったり蹴ったりして追い出され、それが元で死んだ、と書いてあります。児童文学には、時として生々しい現実が顔を出します。いい児童文学は子どもを子ども扱いしませんし、子どもだましでもありません。
私はこの話に、学校教育の普及と家庭崩壊の関係を本能的に見抜いていた人たちを感じます。学校は子どもたちに主に役に立たないことを教え、家庭から労働力を奪う。親の知らないことを教える。抵抗する理由はそこにあります。家族がお互いを必要として生きている形を壊すのです。これに似た話は、日本の『橋のない川』(住井すゑ、一九〇二~一九九七)という小説にも出てきます。
いま、アメリカで、三人に一人の子どもが未婚の母から生まれる。女性の負担は異常に大きくなり、幼児と接する機会を持たない父親に親心(父性)が育たない。優しさと忍耐力が社会から消えていきます。親子関係が柱になって保たれていたモラルと秩序が消え始めると、教育や、警察力や司法の力ではどうにもなりません。子どもが十八歳になるまでに四〇%の親が離婚するのですから、未婚の母から生まれた子どもを足せば、血のつながっている実の両親に育てられる子どもの方が少数なのです。
以前、父親を尊敬しない日本の子ども、という学者によって発表された自虐的な統計があって、アメリカの子どもは日本の子どもより父親を尊敬している、という数字が出ていたのです。これはたぶん「父親のいる子」に質問した結果なのです。対象を父親のいない子まで広げれば比較するべき実態が見えてきます。質問に「実の父親を尊敬しているか」という条件を加え、無作為に選ばれたアメリカの子どもたちに質問すれば、数字はまったく違ってくるのです。「一緒に住んでいる実の父親」とさらに条件を加えれば欧米の数字は惨憺たるものになります。「一緒に住んでいる」ことの大切さを考慮せずに「父親に対する尊敬」を比べ合うのであれば、それこそ問題です。
(尊敬という言葉をどういう英単語に置き換えるかでも数字の意味はずいぶん違ってきます。「リスペクト」つまり、そこに居ることを認める、という意味で使われることが多い単語では、日本人の使う「尊敬」とは随分意味が違います。日本人の使う尊敬は、「アドマイヤー」に近い。)
親心だけでなく「祖父母心」も確実に存在感を失い、家族という定義が一つの大切な次元を失い色あせています。3割から6割の子どもが未婚の母から生まれるということは、自分の孫の存在を知らない、一度も会ったことのない祖父母が相当数いるということなのです。自分の祖父母が亡くなったことを知らない孫たちがたくさんいるということなのです。アメリカで生まれる子どもの二〇人に一人が一生に一度は刑務所・留置所に入るといいます。検挙率が三割に満たないのですから、全員捕まえていたら、たぶん七人に一人は入る。五人に一人の少女、七人に一人の少年が近親相姦の犠牲者といいます。親心という常識が消えると、本来幸せにつながるはずだった人間の愛が、歪んだ形で子どもたちを襲います。
「夢を追うためには仕方がない」ということでしょうか。「アメリカンドリーム」が、夢を持つことではなく欲を持つことであることは想像がつきました。教育の中で、夢を(欲を)抱くことがいかに危険であるかを語る人はいませんでした。やがて、闘いの中で絆を信じることができなくなった男女が、それぞれの夢(欲)を追って経済的安心を求め、自立を目指す。自立は孤立を生みます。社会に蔓延する疑心暗鬼が人生に対する疑いにつながります。子育てが負担となり、自立したい女性を苦しめ、福祉で補おうとするほど親心の喪失が加速します。
ベトナム戦争の終結とともに、児童虐待、女性虐待が一気に増えていきました。徴兵という仕組みを体験し、それに裏切られた時にすでにあった分断や亀裂が深まったのです。それに加えて、子育てが親の手からシステムの手に移ると、社会に優しさと忍耐力がなくなってゆくのです。それが加速してゆく。三〇年前、私が最初の本を書いた当時、毎年六〇万人の子どもが親による虐待で重傷を負い病院に担ぎ込まれていました。それでも経済大国を維持するために、政府は「アメリカンドリーム」を教育の柱に据え競争を煽ったのです。
インドとアメリカ、二〇代に体験し深層を見たこの二つの国の真ん中に、私が見ている現在の日本があります。人類にとって大切な選択肢を考えぬくときです。